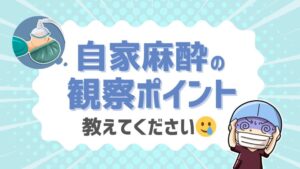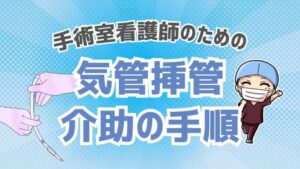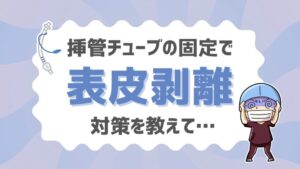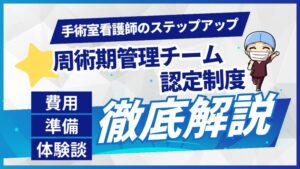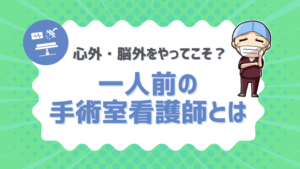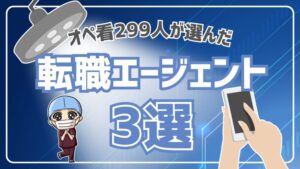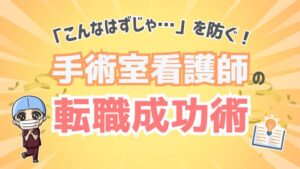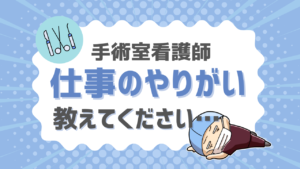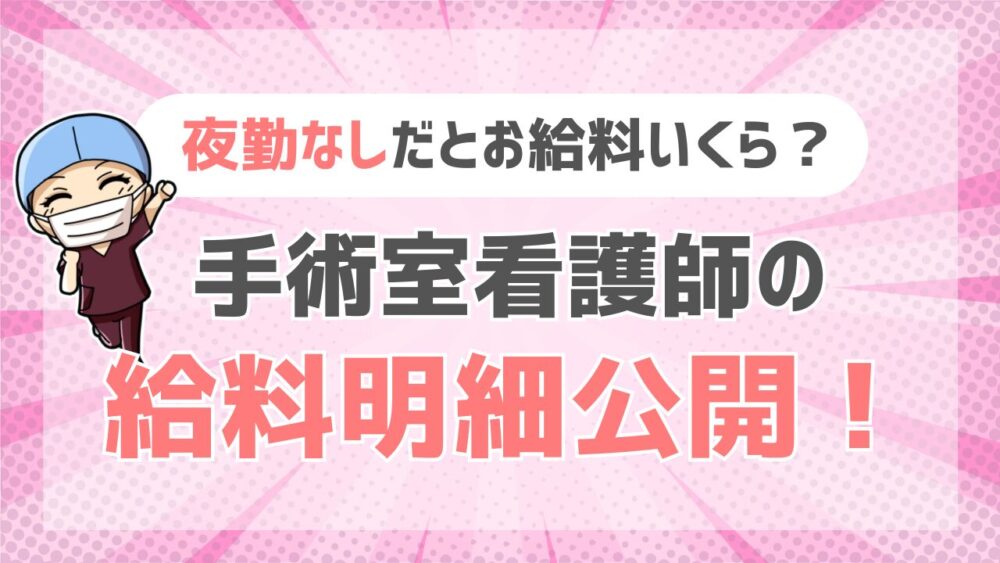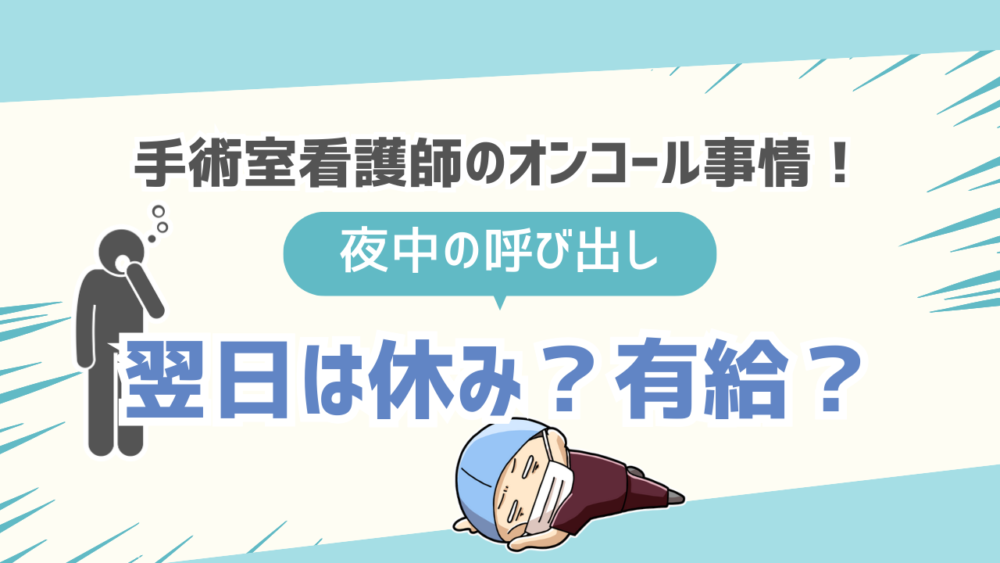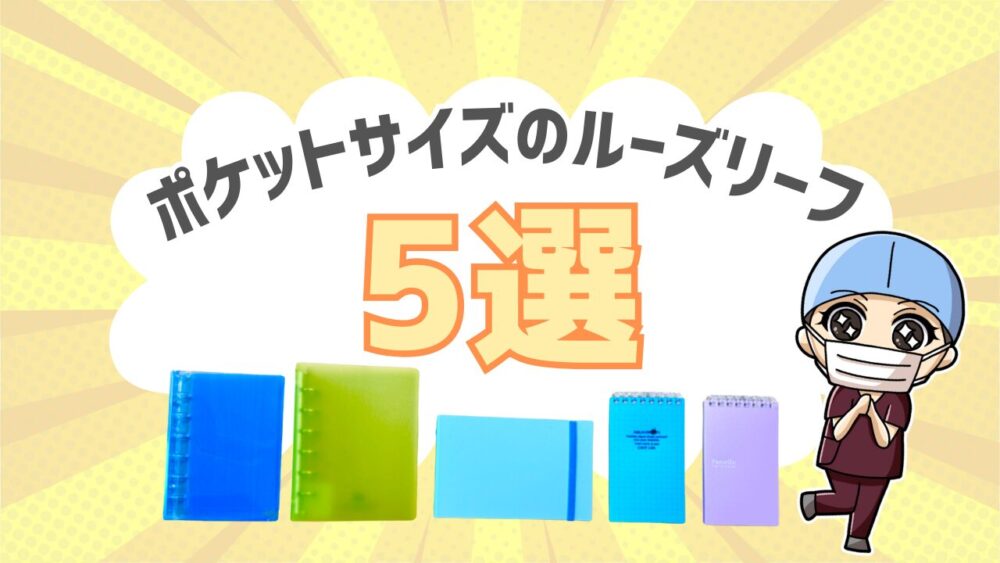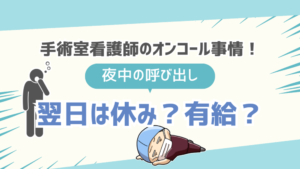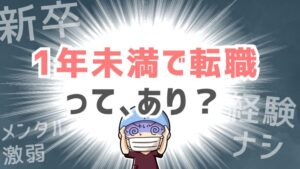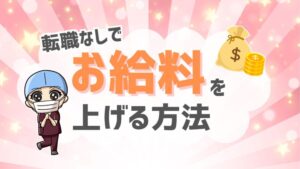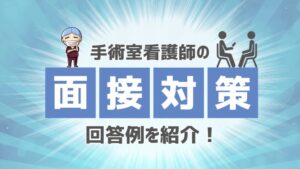手術室が好き!
だから、もっと学びたい!!
そんな想いを抱いている手術室看護師の皆さんに朗報です。
手術室での経験を活かしながら、さらなるスキルアップを目指せる資格がたくさんあります!
今回は、手術室で働く看護師が取得できるステップアップ資格について、詳しくご紹介していきます。
「もっと専門性を高めたい」
「キャリアの幅を広げたい」
という方は、ぜひ参考にしてみてください。


自著
総合医学社「オペ看ノート」

メディカ出版「メディカLIBRARY」
エッセイ:オペナースしゅがーの脳腫瘍日記
クラシコ株式会社「NURSE LIFE MIX」
NLMメイトとして記事連載中
記事:オペ看ラボ
漫画:しゅがーは手術室にはいられない
\フォロワー5万人/
Instagramはこちら
心電図検定
手術室で働いていると、患者さんの状態変化をいち早く察知するために「心電図モニターを読む力」が求められる場面が多くあります。
特に局所麻酔の手術では麻酔科医が不在のケースもあり、外回り看護師が中心となってモニタリングを行うことも。
そのため、心電図の基礎知識があるだけでも、判断力や対応力がぐっと上がります。
心電図検定とは
日本不整脈心電学会が主催する検定試験
心電図に関する知識と判読能力を評価する資格。
心電図検定は、日本不整脈心電学会が主催する、心電図に関する知識や判読力を評価する検定試験です。
医師だけでなく、看護師や臨床検査技師など、幅広い医療従事者が受験しています。
心電図の基礎から、不整脈や虚血性変化の判読、疾患に応じた波形の理解など、レベルに応じて段階的に学べるのが特徴!



手術中にモニターを見ることも多いし、外回りがメインで管理する場面もあるよね。
だからこそ、心電図の知識があるとすごく安心!
この検定は、実際の現場でもすぐに役立つスキルが身につく資格だと思います◎
検定レベル
| レベル | 問題構成・制限時間 | 問題の目安 | |
| 4級 | 心電図の基礎的な判読力を評価 | マークシート方式:70分程度 出題数:50問 | ・モニター心電図(他級より多く含む) ・ホルター心電図の基本的所見 ・12誘導心電図の基本的所見 |
|---|---|---|---|
| 3級 | 基礎〜中等度の判読力を評価 | マークシート方式:90分程度 出題数:50問 | ・基本的な心電図所見 ・危険な不整脈 ・臨床現場でよく出会う不整脈の判読 |
| 2級 | 中等度〜高度な判読力を評価 | マークシート方式:90分程度 出題数:50問 | ・基本的所見、不整脈、虚血性変化 ・疾患による心電図所見の判読 ・ペースメーカの心電図判読 |
| 1級 | 高度な判読力を評価 | マークシート方式:90分程度 出題数:50問 | ・12誘導心電図のエキスパートレベル ・患者状態・疾患・病態からの変化 例)心電図所見から冠動脈狭窄部位推定など ・疾患に関する知識も必要 |
勉強方法
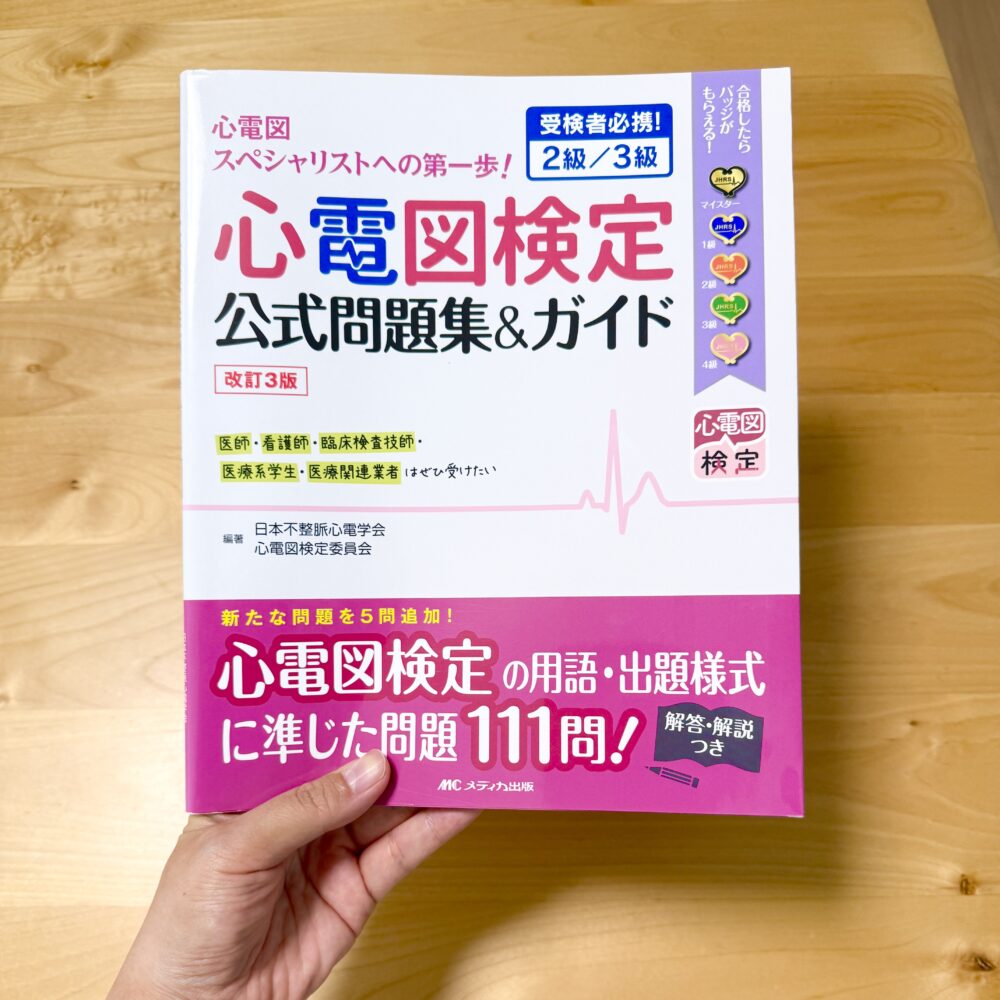
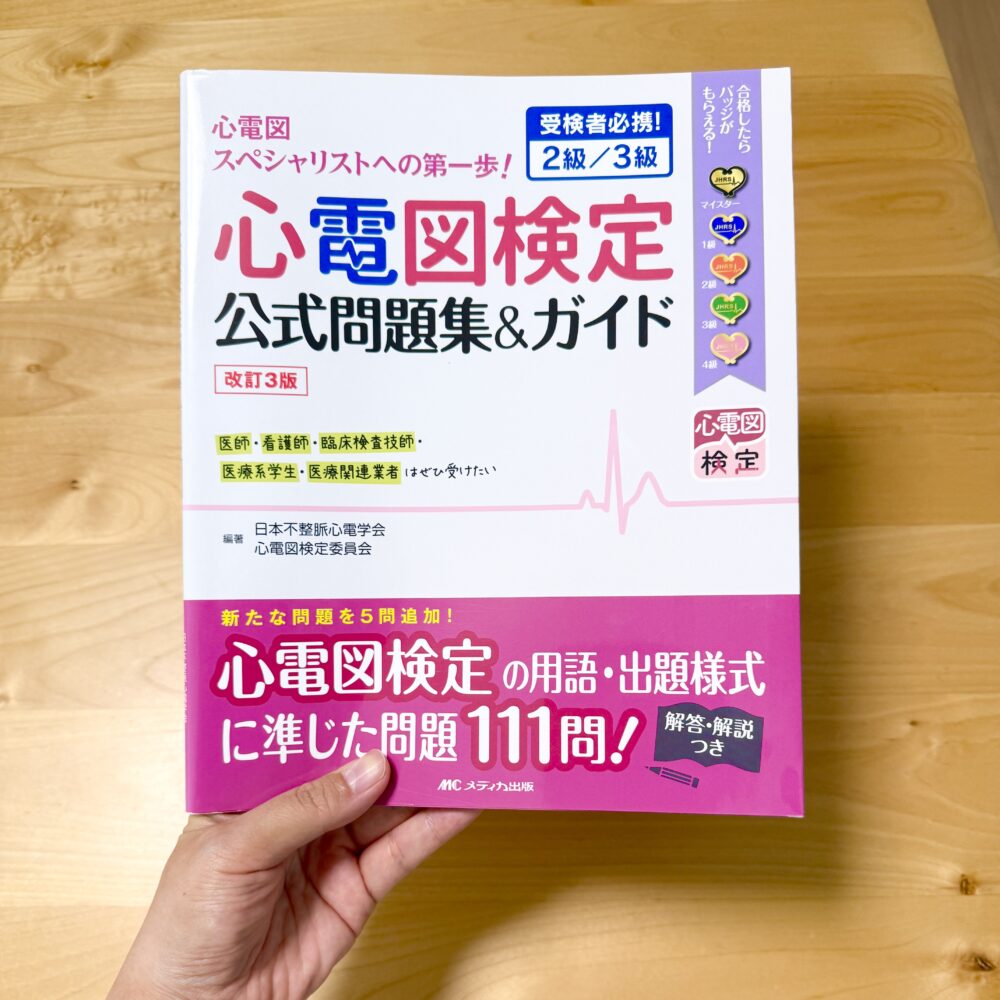
心電図検定の勉強を始めるときは、まず「自分が受ける級のレベル」を知ることが大切です。
4級や3級はモニター心電図や基本的な波形の理解が中心なので、基礎をしっかり学べる市販のテキストや問題集が役立ちます。
日本不整脈心電学会の公式サイトでは「心電図クイズ」も公開されていて、実践的な力を試すのにぴったり。
YouTubeには看護師向けのわかりやすい解説動画も豊富なので、スキマ時間に活用するのもおすすめです。
「なぜこの波形になるのか?」を臨床と結びつけて考えることで、より深く理解できますよ。
滅菌技士/滅菌管理士
手術室で働いていると、器械の洗浄や滅菌の大切さを実感することって多いですよね。
最近では、手術室と中材を兼務する施設も増えていて、「滅菌って意外と奥が深い…」と感じる場面も。
そんな中、「もっと知識を深めたい」「将来、中材の委託会社で働いてみたい」という方にもおすすめなのが、滅菌に関する民間資格です。
滅菌技士・滅菌管理士とは
日本医療機器学会が認定する資格
医療施設における滅菌供給の知識と実践に優れた技士を養成することを目的とした資格。
滅菌技士・滅菌管理士は、医療現場での器材の洗浄・滅菌・供給に関する知識と実践力を証明する民間資格。
滅菌技士は日本医療機器学会、滅菌管理士は日本滅菌業協会が認定しており、それぞれ現場での実務経験や講習の受講を経て、資格を取得するしくみになっています。
中材業務に関わる方や、より専門性を高めたい方におすすめの資格です。



手術室と中央材料室を兼務する病院もあるよね!
中材の委託会社に務めたい!
なんて考えている方もいいかも💡
資格の種類
滅菌技士と滅菌管理士、それぞれ名称や団体は違いますが、どちらも「滅菌のプロ」を目指すための資格です。



受験には実務経験が必要なため、現場での経験を積んだあとにチャレンジする人が多い印象!
滅菌業務に関する知識があると、手術室でも中材でも「なぜその作業が必要なのか」が理解しやすくなり、根拠をもった行動につながりそうですね!
| 項目 | 滅菌技士(滅菌技師) | 滅菌管理士 |
|---|---|---|
| 資格認定団体 | 一般社団法人 日本医療機器学会 | 一般社団法人 日本滅菌業協会 |
| 資格の 種類 | 第1種滅菌技師/第2種滅菌技士 | 滅菌管理士 |
| 認定制度 開始年 | 第2種:2000年 第1種:2003年 | 記載なし(近年需要増加) |
| 受験資格 | 【第2種】 ・日本医療機器学会正会員 ・滅菌業務3年以上 ・講習修了など 【第1種】 ・第2種資格保有 ・学科・実技講習修了 | ・医療現場での滅菌業務実務経験3年以上 ・講習会受講 |
| 試験内容 | 【第2種】 ・講習+筆記試験 【第1種】 ・学科講習+筆記試験 ・実技講習 | ・講習+筆記試験 |
| 資格取得費用 | 【第2種】 ・講習料11,500円+認定料21,000円 【第1種】 ・学科講習30,000円+実技講習30,000円+認定料20,000円 | ▪日本滅菌業協会々員:30,000円(税込) ▪一般(会員外):40,000円(税込) |
| 資格の有効期間・更新 | 【第2種】 4年ごと更新(業務経歴・研修単位等提出、更新料21,000円) 【第1種】 第2種滅菌技士を更新すると、自動的に更新 | 有効期限:3年間 有効期限中に「統一継続研修」の受講で更新 【更新料】 ▪日本滅菌業協会々員:12,100円(税込) ▪一般(会員外):22,000円(税込) |
| 主な業務内容 | ・医療器材の洗浄、組立、包装、滅菌処理 ・滅菌保証、記録管理 ・医療現場への供給 ・第1種は指導・管理も担当 | ・滅菌業務全般 ・管理業務(書類作成、機器点検、在庫管理) ・教育業務(スタッフ指導) |
| 国家資格か | 民間資格 | 民間資格 |
| 活躍の場 | 病院、クリニック、歯科医院、滅菌受託業者、関連メーカー等 | 病院、クリニックなど医療現場 |
| 資格取得のメリット | ・滅菌業務の知識・技術の証明 ・就職・転職で有利 ・院内感染対策のPR | ・専門知識・技術の証明 ・安全な医療提供に貢献 |
3学会合同呼吸療法認定士
手術室やICUなど、呼吸管理が必要な現場で働いていると「もっと深く学びたい」と感じること、ありませんか?
そんな方におすすめなのが「3学会合同呼吸療法認定士」。
人工呼吸器や酸素療法など、呼吸療法に関する専門知識を身につけることができます。
准看護師でも条件を満たせば受験できるのも魅力のひとつです!
3学会合同呼吸療法認定士
日本胸部外科学会、日本呼吸器学会、日本麻酔科学会の3学会が合同で創設
呼吸器疾患を持つ患者に対して専門的な呼吸管理を行うための認定資格。
3学会合同呼吸療法認定士は、日本胸部外科学会・日本呼吸器学会・日本麻酔科学会の3つの学会が共同で設けた認定資格。
人工呼吸器の管理や酸素療法など、呼吸療法に関する専門的な知識と技術を身につけた医療従事者を対象に認定が行われます。
手術室や集中治療室など、呼吸管理が重要となる現場で活かせますね!



手術室やICUなどに勤務する看護師が多く取得しているそうです!
受験内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象医療職種と実務経験 | ・臨床工学技士、看護師、理学療法士、作業療法士:実務経験2年以上 ・准看護師:実務経験3年以上 |
| その他の受講要件 | 受講申込時から過去5年以内に、認定委員会が認める学会・講習会などに出席して12.5点以上の単位を取得していること |
| 認定講習会受講料 | ・会場 + e-ラーニング:30,000円(税込) ・e-ラーニングのみ:20,000円(税込) |
| 認定試験受験料 | 10,000円(税込) |
| 認定登録料 | 3,000円(税込) |
| 試験時間 | 2時間50分 |
| 問題数 | 100問 |
| 試験形式・会場 | 東京都内の会場にて、マークシート形式で実施 |
| 総費用目安 | 会場受講の場合:43,000円(税込) (講習会30,000円+受験料10,000円+登録料3,000円) e-ラーニングのみの場合:33,000円(税込) (講習会20,000円+受験料10,000円+登録料3,000円) |



准看護師でも受験できる💡
周術期管理チーム認定制度
注目されている「周術期管理チーム認定」。
手術を安全に行うためのチーム医療に必要な視点や知識を深められる資格で、看護師だけでなく、薬剤師や臨床工学技士も対象となっています。



私も挑戦したことがありますが、実践に活かせる学びがたくさんありました!
周術期管理チーム認定とは
患者の手術前から手術後までの周術期医療に携わる医療専門職のための認定制度
看護師だけでなく、薬剤師、臨床工学技士も受験できる多職種向けの資格。
周術期管理チーム認定は、手術の前後(術前・術中・術後)を通じて患者さんを安全にサポートするための、知識とスキルを証明する認定資格です。
日本麻酔科学会が運営しており、看護師だけでなく、薬剤師や臨床工学技士も対象となる多職種向けの制度。
周術期のチーム医療に必要な視点や連携力を深めることができ、実際の現場でもすぐに活かせる内容が学べます。
受験条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 看護師の要件 | 実務経験:麻酔科標榜医が年間200症例以上の麻酔管理を提供している施設での手術室、または周術期管理センター等の勤務が満2年以上 申し込み条件: ・日本麻酔科学会主催・共催の周術期管理チームセミナーを2回受講 ・日本手術看護学会主催の年次大会または麻酔看護研修に2回参加 |
| 薬剤師の要件 | 実務経験:病院・診療所勤務歴を3年以上有し、そのうち2年以上の周術期関連の実務経験があること 申し込み条件: ・日本麻酔科学会主催・共催の周術期管理チームセミナーを2回受講 |
| 臨床工学技士の要件 | 実務経験:手術室、周術期管理センターまたは集中治療部(救急部門含む)の臨床経験が3年以上であること 申し込み条件: ・日本麻酔科学会主催・共催の周術期管理チームセミナーを2回受講 ・日本臨床工学会または日本臨床工学技士会主催もしくは共催のセミナーを1回受講 |
| 受講期間 | 申請する年の3年前の4月1日から申請する年の3月31日までの間に受講したもの |
| e-learning | 1講座3,300円(税込)、5ポイント(5講座受講)でセミナー1回分相当 |
| 費用詳細 | セミナー受講費: ・麻酔科学会主催・共催セミナー:11,000円/回 ・e-learning:3,300円/講座(5講座で16,500円=セミナー1回分) 第37回日本手術看護学会年次大会の参加費 ・会員:8,000円 ・非会員:15,000円 認定試験受験料(審査料):11,000円(税込) 登録料:22,000円(税込)※合格後に支払い |
| 総費用目安 | 約8~9万円(セミナー受講方法や回数によって変動) 例:セミナーの受講2回(22,000円)+年次大会の参加2回(30,000円)+審査料(11,000円)+登録料(22,000円)=85,000円 |
| その他 | 特定行為研修や術後疼痛管理研修へのステップアップが可能 |



勉強するのは大変だったけど、手術室で使う知識を深められたよ!
勉強方法
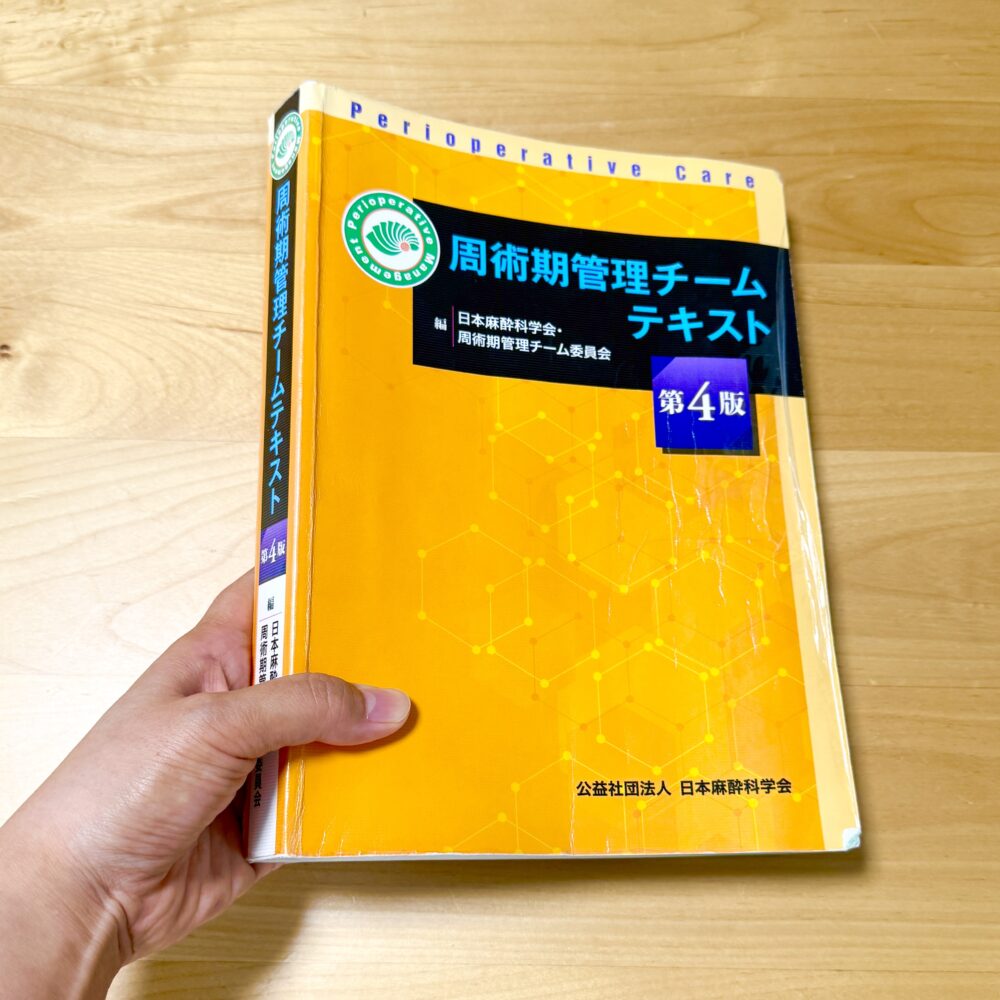
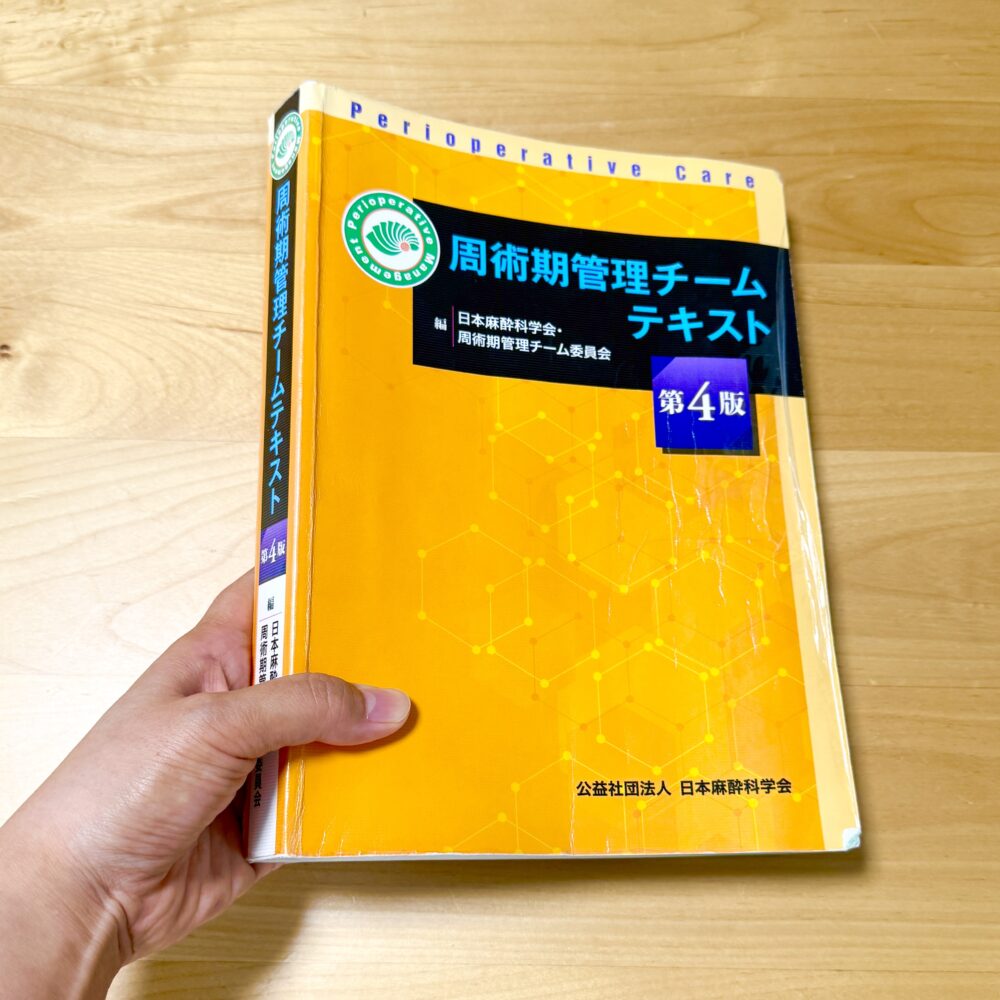
周術期管理チーム認定の勉強は、公式テキストとガイドラインを中心に進めるのがおすすめです。
試験は、周術期管理チームテキストや各学会のガイドラインから出題されるため、内容をしっかり読み込むことが大切。
公式HPでは過去問も一部公開されており、出題傾向をつかむのに役立ちます。
特定看護師
特定看護師とは、医師や歯科医師の包括的な指示のもと、「特定行為」と呼ばれる高度な診療補助を自律的に実施できる看護師のこと。
資格ではありませんが、制度に基づく重要なキャリアパスのひとつとして注目されています。
特に手術室では、気管チューブの位置調整や鎮静薬の調整、動脈ラインの確保など、活かせる特定行為が多く含まれています。
実践力を高めたい方にとって、大きなステップアップになる制度です。
特定看護師とは
医師や歯科医師の包括的な指示のもと、特定行為と呼ばれる高度な診療補助業務を自律的に実施できる看護師
※特定看護師は「資格」ではありませんが、キャリアアップの選択肢として重要なので紹介します。
38行為ある特定行為の中で、手術室で活躍できそうなもの
- 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整
- 人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整
- 橈骨動脈ラインの確保 など



気になる方は、38行為はどんなものがあるのか見てみてね~!
日本麻酔科学会特定行為パッケージ研修とは
日本麻酔科学会特定行為パッケージ研修は、高度急性期医療において看護師が麻酔科専門医の指示のもと、より自立してケアを行えるようにするための研修プログラムです。
この研修は、日本麻酔科学会認定病院および協力施設に勤務する看護師を対象としています
受験内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象職種 | 日本麻酔科学会認定病院かつ協力施設に勤務している看護師 |
| 受講資格 | ・日本麻酔科学会が認定する「周術期管理チーム看護師」の資格を有していること ・自施設で研修が実施可能であること(協力施設での勤務実態があること) ・自施設が日本麻酔科学会の協力施設であること ・現在勤務している所属施設の「日本麻酔科学会代表専門医」および「看護部長」の推薦状を有していること ・上記要件を出願期間中から研修期間中まで満たしていること |
| 受講料 | 30万円(税別) ※共通科目・区分別科目をすべてパッケージで受講する場合 ※2024年4月1日付の価格 |
| 研修期間・方法 | 期間:原則として約1年間 方法:講義(eラーニング)、演習、OSCE(客観的臨床能力試験)、実習、評価のすべてを自施設(協力施設)で実施 特徴:就労しながら受講が可能 |
| 共通科目 (252時間) | ・臨床病態生理学:講義・演習・試験(31時間) ・臨床推論:講義・演習・実習・試験(45時間) ・フィジカルアセスメント:講義・演習・実習・試験(45時間) ・臨床薬理学:講義・演習・試験(45時間) ・疾病・臨床病態概論:講義・演習・試験(41時間) ・医療安全学・特定行為実践:講義・演習・実習・試験(45時間) |
| 区分別科目 (70時間) 6区分8行為 | 1. 呼吸器(気道確保に係るもの)関連(9時間) 特定行為:経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 2. 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連(17時間) 特定行為:侵襲的陽圧換気の設定の変更、人工呼吸器からの離脱 3. 動脈血液ガス分析関連(13時間) 特定行為:直接動脈穿刺法による採血、橈骨動脈ラインの確保 4. 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連(11時間) 特定行為:脱水症状に対する輸液による補正 5. 術後疼痛管理関連(8時間) 特定行為:硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整 6. 循環動態に係る薬剤投与関連(12時間) 特定行為:持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整 |
| 総研修時間 | 322時間(共通科目252時間+区分別科目70時間) |
専門看護師®(CNS)
専門看護師®とは
特定の看護分野で高度な知識と技術を持つスペシャリスト
患者・家族へのケア、医療チームの支援、教育、研究など多岐にわたる役割を担う。
専門看護師®とは、特定の看護分野において高度な知識と実践力を持ち、ケアの提供だけでなく、相談・調整・倫理調整・教育・研究といった役割も担う看護師のこと。
公益社団法人日本看護協会が認定する資格で、がん看護や急性・重症患者看護などがあります。
看護系大学院での修士課程修了や実務経験など、取得には一定の要件がありますが、専門性を深めたい方にとっては大きなキャリアアップにつながります。
専門看護分野
専門看護師®は分野が多く、自分の関心や経験に合わせて選べるのが魅力です。
手術室での経験って、実はさまざまな専門分野につながっていて、キャリアの選択肢も広がるんだなと感じました。
興味がある分野があれば、ぜひ調べてみてくださいね。
現在、特定されている分野は以下の14分野です。
| がん看護 精神看護 地域看護 老人看護 小児看護 母性看護 慢性疾患看護 | 急性・重症患者看護 感染症看護 家族支援 在宅看護 遺伝看護 災害看護 放射線看護 |
取得費用は300万⁉
私の先輩は、「急性・重症患者看護」分野の専門看護師®を目指して、手術室からICUへ転職していました。
専門看護師になるには大学院での学びが必要で、費用も約300万円ほどかかるそう。
先輩はそのために、資格取得を支援してくれる制度がある病院を探していました。
本気で目指すなら、働きながら学べる環境やサポート体制も大事ですね。
認定看護師®(CN)
認定看護師®とは
水準の高い看護を実践できると認められた看護師
認定看護分野には「手術看護」も含まれており、手術室看護師にとって専門性を高めるうえで有力なキャリアの選択肢のひとつ。
認定看護師®(Certified Nurse:CN)とは、特定の分野において水準の高い看護実践ができると認められた看護師のことです。
日本看護協会が認定する制度で、実務経験や所定の教育課程の修了が必要。
役割は主に「実践・指導・相談」で、臨床の最前線で活躍することが期待されます。
専門看護師と認定看護師の比較
| 専門看護師 | 認定看護師 |
|---|---|
| 実務研修5年以上 うち3年以上は専門看護分野 | 実務研修5年以上 うち3年以上は認定看護分野 |
| 役割は、実践、相談、調整、 倫理調整、教育、研究 | 役割は、実践、指導、相談 |
| 看護系大学院の修士課程で 所定の単位を取得 | 認定看護師教育機関で所定の カリキュラムを修了 |
取得費用は約120万⁉
認定看護師®を目指すには、教育機関で6か月~1年程度の研修を受ける必要があり、その費用はおおよそ100万〜130万円ほどと言われています。
取得には金銭的な負担は少なくありません。
ただし、病院によっては資格取得を支援する制度がある場合も!
将来のキャリアを見据えて、勤務先の支援制度を調べておくのがおすすめです。
おわりに
手術室で働く看護師には、多様なキャリアアップの道が開かれています。
心電図検定のように段階的に学べる資格から、専門看護師のような高度な専門性を追求する道まで、自分の目標や興味に合わせて選択できます。
今の働き方を続けながら専門性を深めるもよし、新たな分野に挑戦するもよし。
どんな道を選んでも、これまで手術室で積み上げてきた経験は、必ずあなたの強みになります。
「ちょっと気になるな」と思った資格があれば、まずは調べてみるところから!
自分のペースで、未来の選択肢を広げていきましょう。