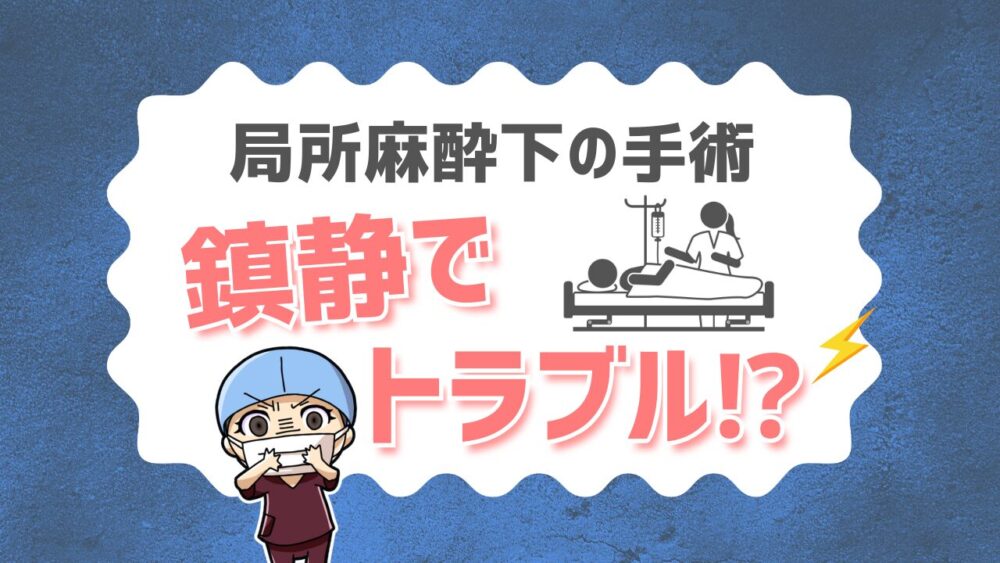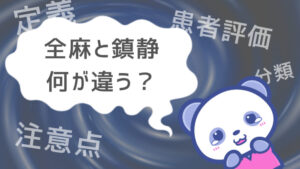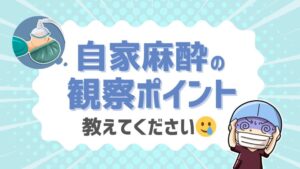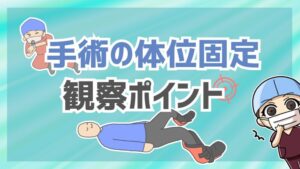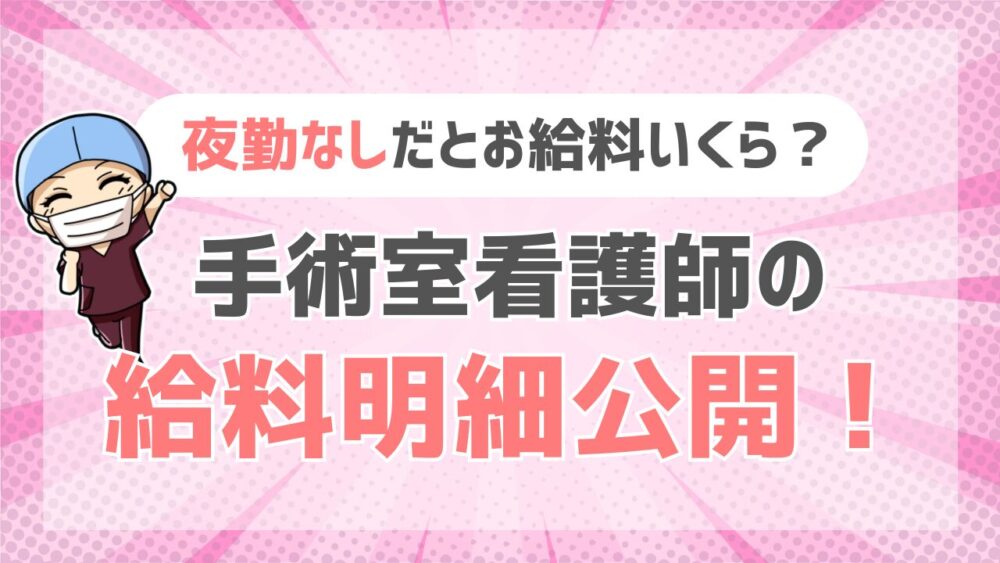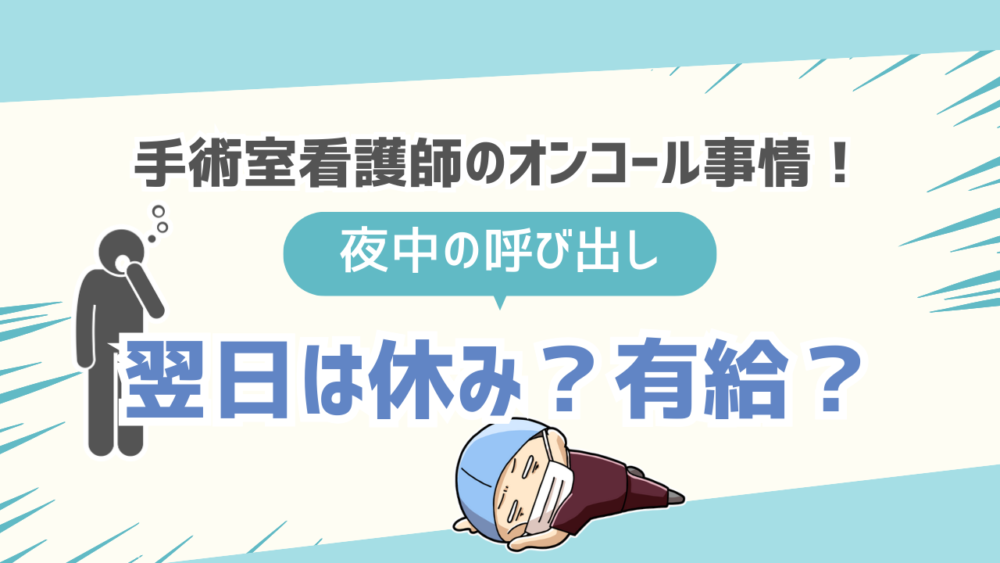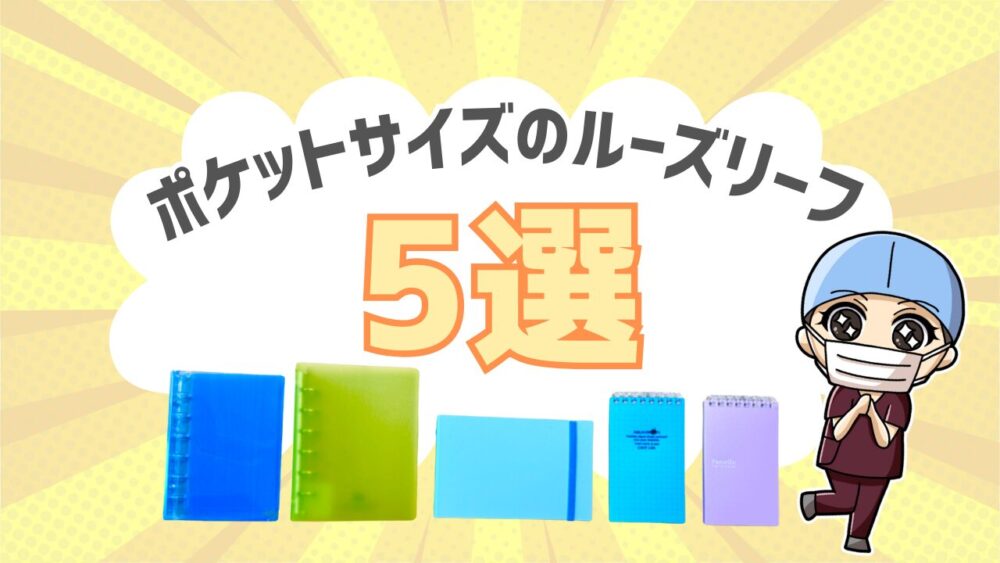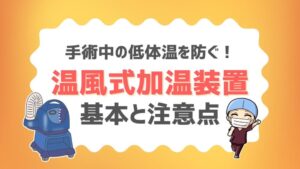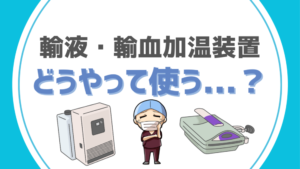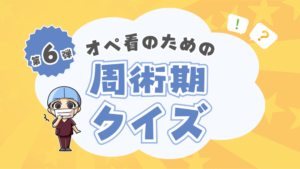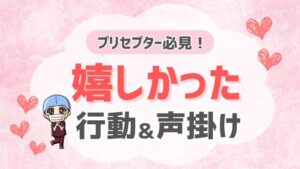手術室で欠かせない麻酔。
その中でも、全身麻酔ではなく局所麻酔下で行われる手術があります。
患者は完全に眠っているわけではないので、痛みや不安で術中に「身体が動いてしまう」というシーンも…。
手術の安全性を保つためには適切な鎮静管理が重要ですが、一方で過鎮静による呼吸抑制のリスクも考慮しなければなりません。
現場では「体動があった時はどう対応すればいいの?」「鎮静薬の使い分けはどうしてる?」「過鎮静になったらどうするの?」といった声をよく耳にします。
そこで今回は、局所麻酔下手術での体動への対応について、実際の手術室看護師が使用している薬剤の組み合わせ、現場での具体的な対応方法、過鎮静時の対処法まで、実体験に基づいた情報をまとめてご紹介します。
この記事は、筆者のInstagramのストーリーズに設置した質問BOXを通じて、フォロワーさんから寄せられたリアルな声やDMのコメントをもとに作成しています。実際の現場での工夫や体験談をご紹介していますが、あくまで一例であり、情報によって生じた不利益・損害等については一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

自著
総合医学社「オペ看ノート」
メディカ出版「メディカLIBRARY」
エッセイ:オペナースしゅがーの脳腫瘍日記
クラシコ株式会社「NURSE LIFE MIX」
NLMメイトとして記事連載中
記事:オペ看ラボ
漫画:しゅがーは手術室にはいられない
\フォロワー5万人/
Instagramはこちら
局所麻酔下の手術に使われる薬剤

局所麻酔の手術、本当に悩ましいですよね。
自家麻酔でデクス+ミダゾラムを使っても体動が出てしまうことはありますし、「これが正解!」という明確な答えがないのが難しいところ。
四肢抑制も万能ではなく、患者さんによっては動いてしまいますよね、、、
よく使用される薬剤と特徴
| 薬剤 | 特徴 |
|---|---|
| ベンタゾシン (ソセゴン®など) | 血圧がやや上昇させる効果がある。 そのため、血圧が低めの患者に好んで使用される。 |
| ヒドロキシジン塩酸塩 (アタラックス®-Pなど) | 中枢神経系に作用し、不安や緊張を和らげる作用がある。 |
| ミダゾラム (ドルミカム®など) | 拮抗薬(フルマゼニル)によるリバースができる。 |
| デクスメデトミジン (プレセデックス®) | 調節性は劣るが呼吸抑制がほとんどなく安全性が高い。 |
| プロポフォール | 鎮静深度が調節しやすく、覚醒が早い。 |
薬剤の選択や投与は麻酔科医が中心ですが、看護師も観察と報告で大きな役割を担っています。
特に投与後のちょっとした変化に気づけるのは、すぐそばで寄り添っている手術室看護師なんですよね。
でも、薬剤って安心を与える一方で、使い方を間違えると合併症につながることも…。
だからこそ早めに異変をキャッチすることがすごく大事。
「この薬を使ってるから、こういうリスクがあるかも」と意識しておくだけで、対応の速さも全然変わってきます。
鎮静と鎮痛はセットが多い!
局所麻酔下での手術や処置では、患者さんの不安や痛みをどうコントロールするかがとても大切です。
そこで登場するのが「鎮静」と「鎮痛」。
似ているようで、実は役割が違うんです。
- 鎮静薬:不安や意識を和らげる
- 鎮痛薬:痛みを抑える
役割が違うので、状況に応じて「組み合わせて使うこと」がポイントになります。
侵襲度の高い処置では、鎮静だけではカバーしきれないんです。
- 痛みが強いと、不穏や動きの原因になる
- 鎮痛が不十分だと、鎮静薬を過量に投与してしまう
- 鎮痛をしっかり行うことで、副作用を減らせる
- 患者さんの安心感や満足度がアップする
つまり「痛みを取ること」が、安定した鎮静管理につながります。



「眠らせれば痛くない!」は大間違い。
ちゃんと痛み止めを使うことで、鎮静
薬の量も減らせて安全!
鎮静薬の過剰投与による合併症(呼吸抑制など)を防ぐには、鎮痛を優先する「analgesia-first sedation」の考え方が重要です。



「安全な鎮静のためのプラクティカルガイド」は、日本麻酔科学会が作成した非手術室領域での鎮静を安全に行うための実践マニュアルなんだけど、手術室でも参考になるかと思って引っ張り出してきました。
局所麻酔下で行う手術、鎮静方法は?
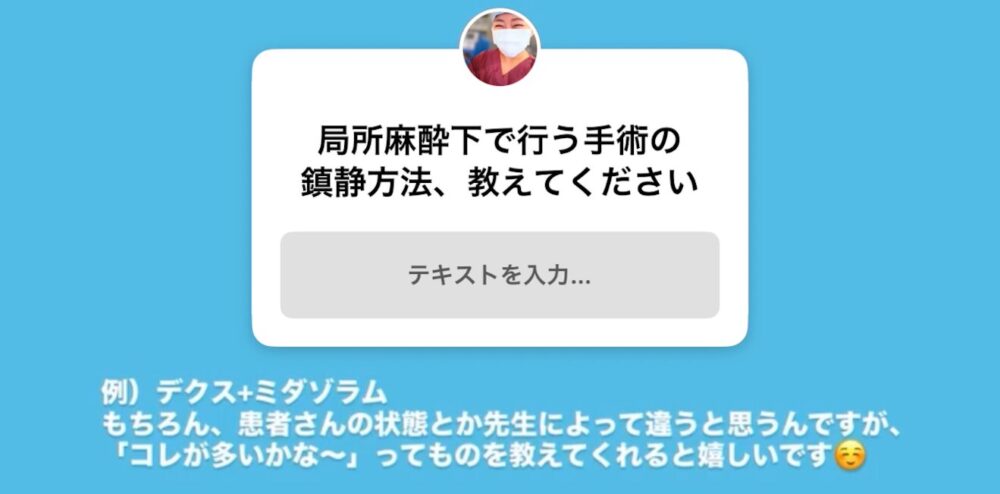
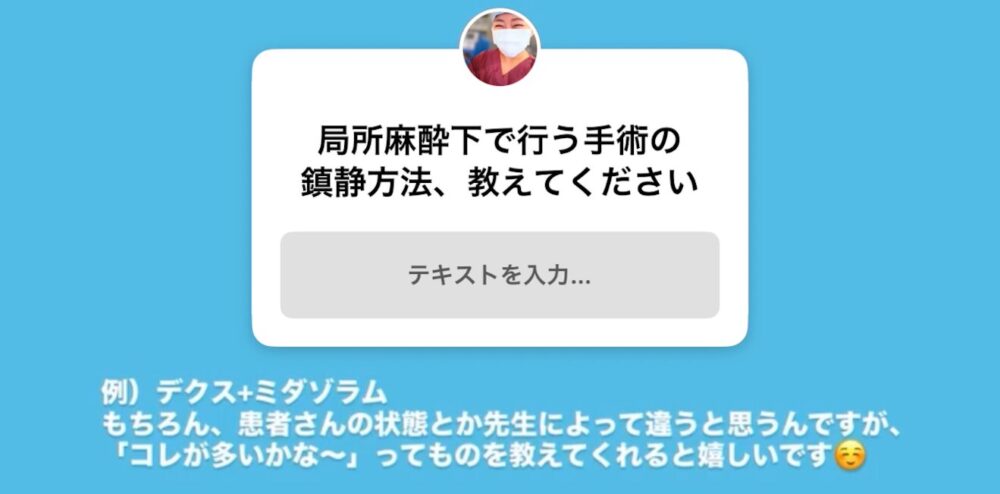
ベンタゾシン+ヒドロキシジン塩酸塩(ソセゴン®+アタラックス®ーP)
よく使われる「ソセアタ」の組み合わせ。
鎮静効果が強くでるので呼吸抑制に注意が必要です。
鎮静薬:アタラックスーP
鎮痛薬:ソセゴン



PMは新規も電池交換も基本、ソセゴン半筒とアタラックスP1Aです。
ごく稀にプロポ…。



生食50にソセアタが主です!
あとは指示でフェンタをいったりプロポを使うこともあります。



私もオペ室兼カテ室です!
うちではソセゴン + アタラックスP + 生食をdrip。
覚醒体動時は追加です。



ペースメーカーだと術前にソセゴンやアタPを筋注してから入室して、音楽を聞いてもらい高原オペしてます。



PMIではソセアタで鎮静してます!
EVLAではプロポフォール使ってます。
舌根沈下が怖い…。



ペースメーカーは局所麻酔と必要時にソセアタくらいです!
肝・膝上・足首をベルトで固定してます。
ベンタゾシン+ミダゾラム(ソセゴン®+ドルミカム®)
鎮静薬:ドルミカム
鎮痛薬:ソセゴン



ミダゾラムとソセゴンが多いです。



ソセゴン + ミダゾラムが多いです。



ソセゴン、ミダゾラム
デクスメデトミジン(プレセデックス®)
鎮静薬:プレセデックス
併用でソセアタなど



DEX+コントミンカクテルを使ってますが、かなり体動が強いです…



プレセデックスをよく使います。
ソセアタと併用する事もあります。



基本デックスですね。
痛みが強かったりする時はソセアタを追加で使ってます。
プロポフォール
鎮静薬:プロポフォール
鎮痛薬:フェンタ、ドルミカムなど



プロポもけっこう使います!
下肢は二重抑制帯、動き出したら手も抑制帯をします。
循内以外の科はプレセデックスがほとんどです!



ペースメーカー、アブレーションのときはプロポ持続とフェンタ持続です。
因みに各科管理…



ミダゾラム、プロポフォールが多いです
基本、鎮静しない



基本、ノー鎮静。
必要時、アタP、ソセゴン、ホリゾン等使用!!



鎮静しません。
キシロのみです。



PM挿入時は基本、鎮静ナシでした。
体動がある時はミダゾラムを使用してましたが、めったにありませんでした。



私がいた手術室も、基本的に鎮静なしだったけど…
動いてしまいそうな時は事前に執刀医や麻酔科医に相談してた。
術中、体動がある時の対応は?
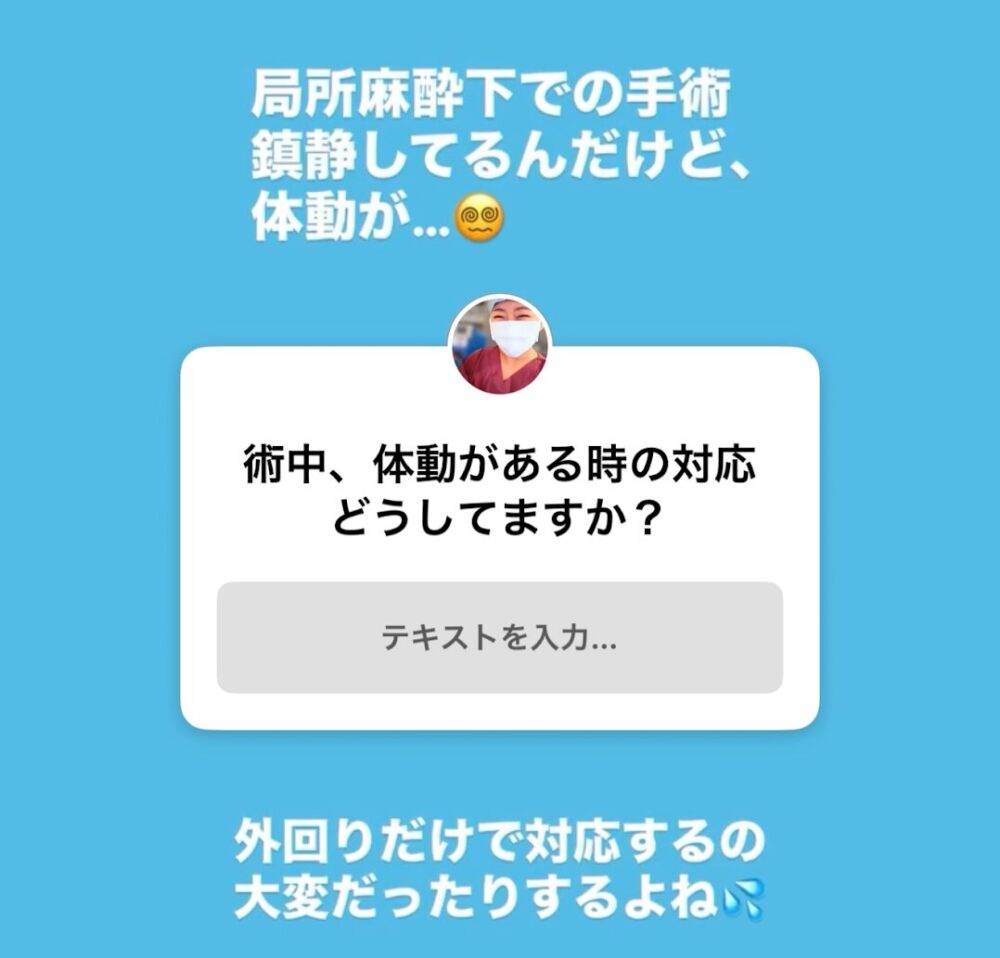
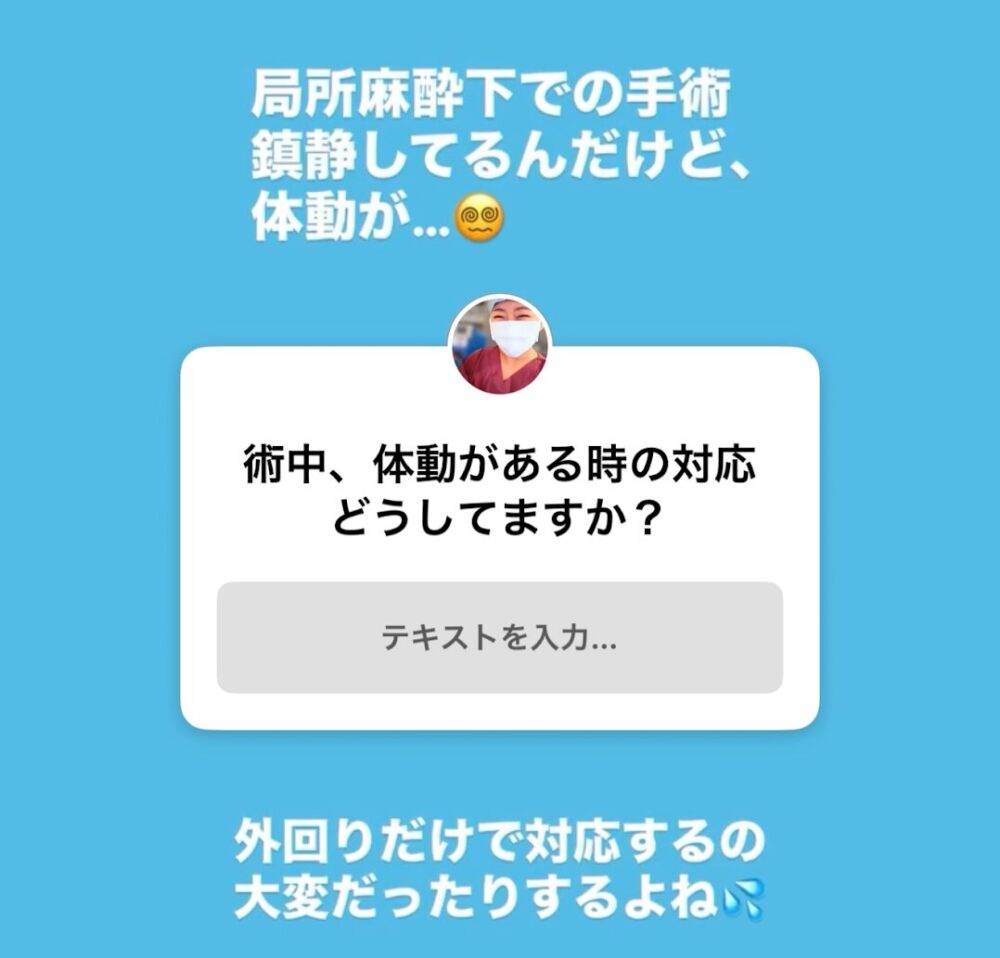
局所麻酔下の手術では、鎮静をかけていても患者さんが動いてしまうこともありますよね。
術者の視野に影響が出たり、創部に手が伸びてしまったりと、外回りだけで対応するのはなかなか大変です。
みなさんはどう対応されているのでしょうか。
抑制帯で固定



体幹抑制できるよう念のため準備はして開始してます。
アタラックスP 1/2A、ソセゴン 1/2A 静注したり。



体幹+四肢固定!
(患者に鎮静がかかる前に許可を得てさせてもらってます)



ペースメーカー挿入時は基本全症例手足を抑制帯(グリップ)で固定しています!
患者さんには説明済



基本的には四肢をベルトで抑制して、それでも無理なら先生とか外回りが抑制してます



手は抑制バンド(紐付き)でレールなどに巻き付けてます。



手術前に説明と同意が得られているのか(同意書)確認しなきゃ!
応援を呼ぶ



応援よんで押さえてもらいます!



人を呼びます!
リーダーさんとか師長さんでも!
あとは先生に薬追加の指示をお願いしてます!



空いているスタッフに来てもらい抑えてます…



放射線技師さんや、人を呼んでます



医師の指示のもとで鎮静を深くするか、応援を呼んでひたすら抑えます
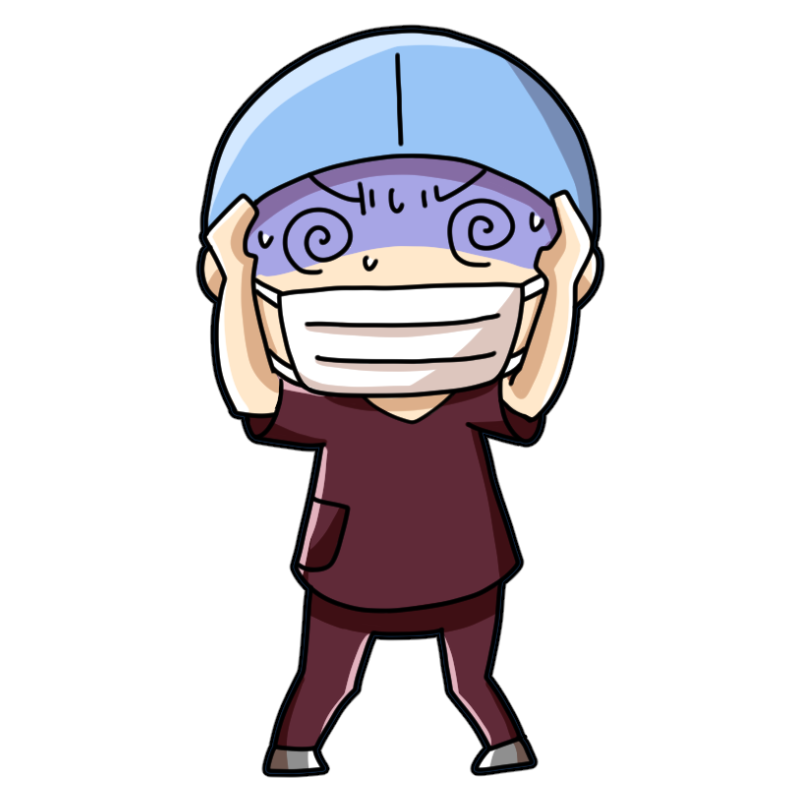
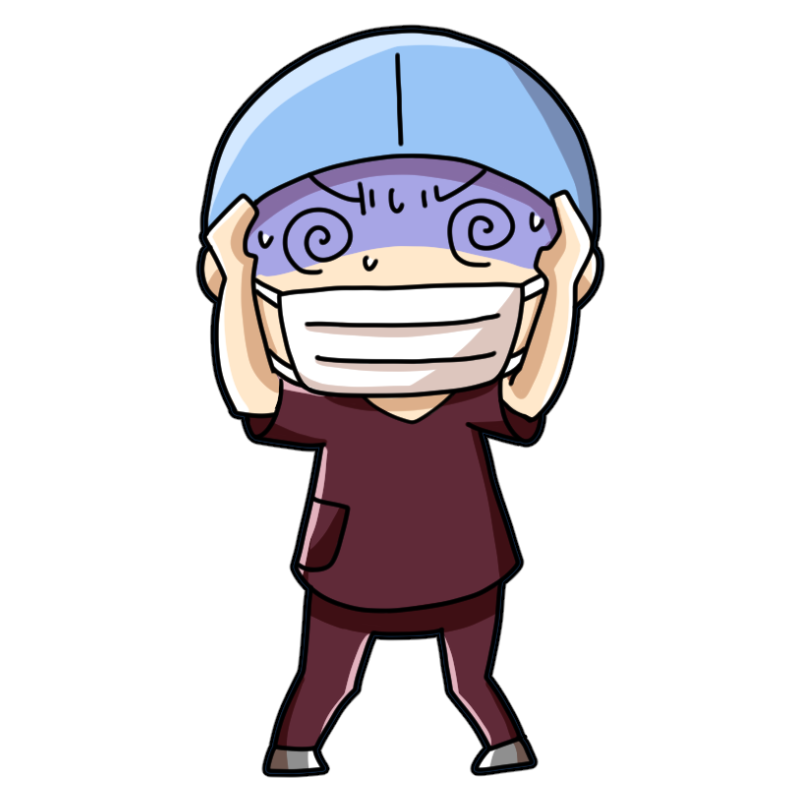
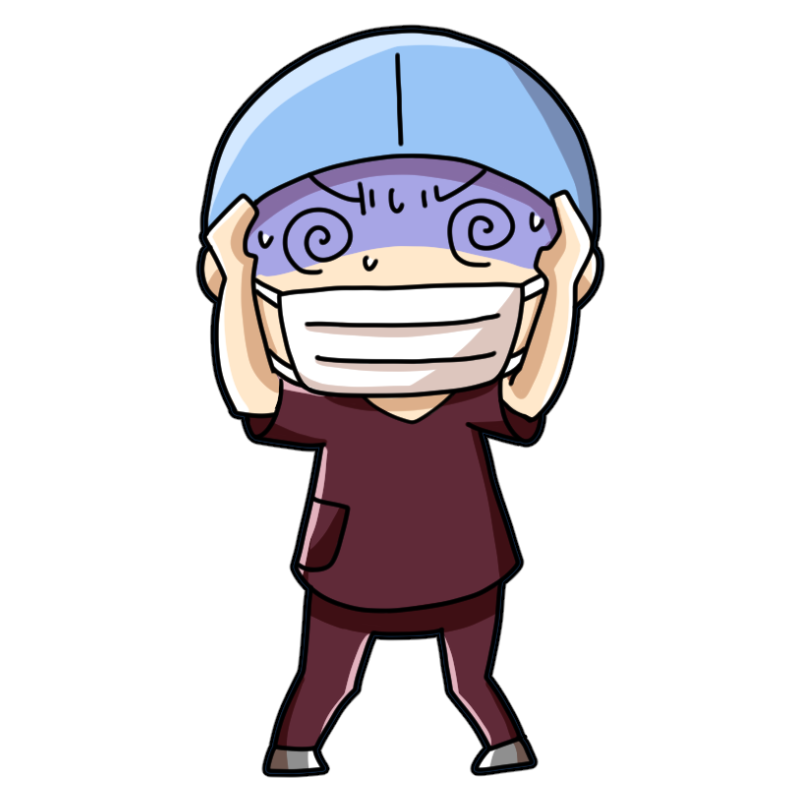
術式によっては、執刀医と外回りの2人だけ…
そんなこともが多い。
早めに応援を呼べるといいですよね!
抑える



外回りがおさえてます。
あまりにも激しい場合は鎮静。



鎮静かけたらフラッシュするか、それでも動く時は申し訳ないですが看護師が抑えてます。



ひたすら抑える。



外回りが抑えに行くか、ミダゾラム追加投与指示があったりします!



手術中は動かれると、とても危険。
でも、強く抑えることはできれば避けたい…。
どうすれば安心して動かずにいられるか…いつも悩むよね…。
患者の手を握る



患者さんの横で手を握ります。
症例によりミダゾラム、デクスメデトミジンを使用です。



人に余裕があったら手を握ってもらう係してもらいます!
余裕があったらですが…。
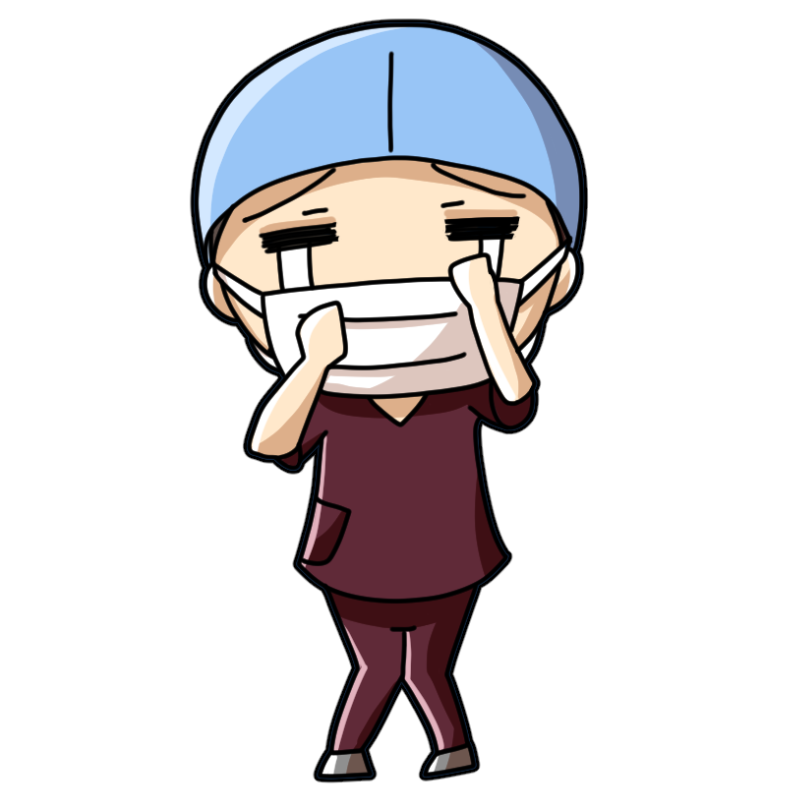
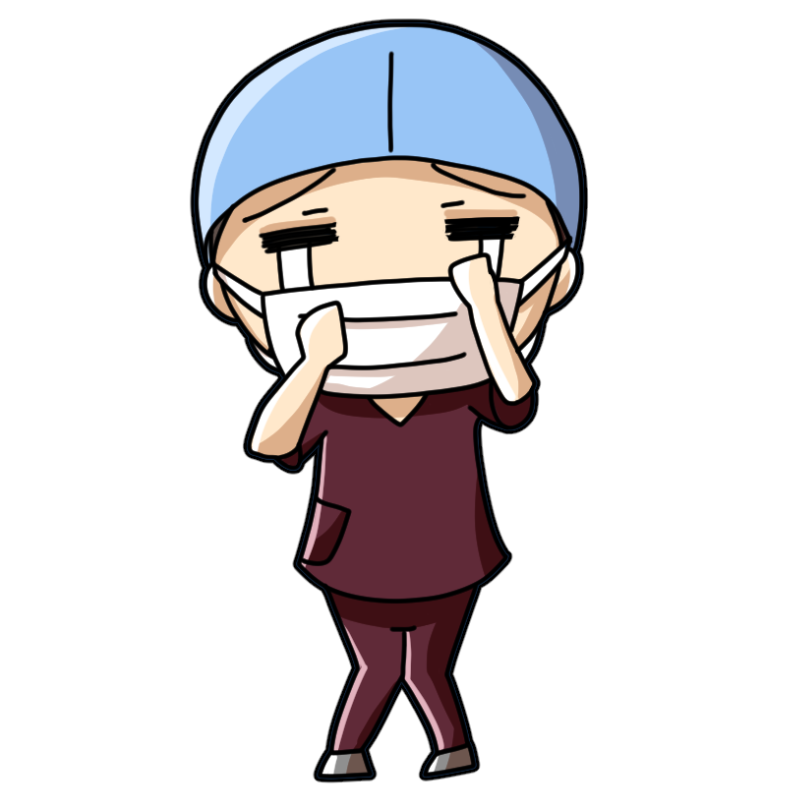
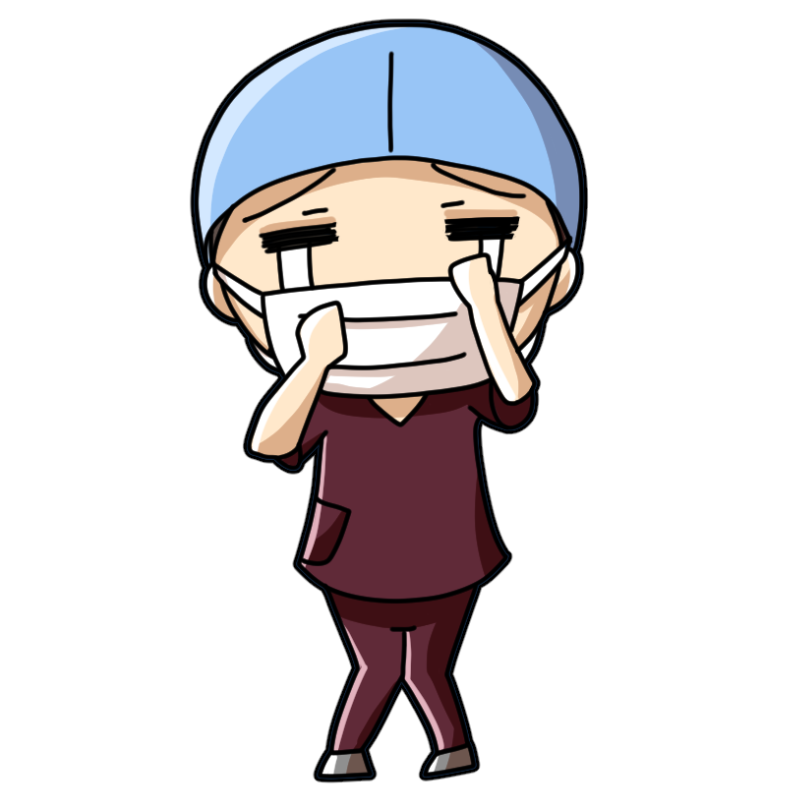
「抑える」って、患者さんにとってもしんどいし、私たちにとってもしんどい。
だからこそ、少しでも安心してもらえるように、そっと横で手を握っていられたらいいなって思う。
でも、忙しいときほど、ゆっくり向き合う余裕がないのが現実だったりするんだよね…。
麻酔科を呼ぶ



局麻のみで鎮静してません。
カテ室で安静保持困難な場合は麻酔科を呼んでプロポ+DXかなあ…



執刀医に指示を仰いでいますが、対応してくれなさそうな時は麻酔科医長を呼んでます!



先生に相談して追加で投薬することが多いです。



麻酔科のインチャージを呼ぶ!



先生との関係性って、やっぱり大事。
正直、状況やタイミングによってはお願いしづらい時もある…。
だからこそ、普段から話しやすい関係を作っておくのって大切だなって思う。
外回り2人体制!



局麻オペは外回り2人なので、1人は患者の横に立って対応したり、物を出したりしてます!



これは…っ!!
理想ですね!!
過鎮静への対応



オペ始まる時にソセゴン、アタラP、術中体動あればプレセデックスです。
この間、認知症の方でそれ+プロポフォールいって過鎮静になり挿管しました。
怖かったです…。



怖すぎる!
自家麻酔で鎮静して舌根沈下や呼吸抑制が起きた場合の対応も確認しておきましょう。
麻酔器、カートの物品をチェック
局所麻酔下の手術でも、途中から全身麻酔になる可能性はゼロではありません。
そのため、事前に麻酔器のチェックやカートの物品確認を行っておくことが重要です。
- 酸素マスク(麻酔器の酸素バック・蛇管・人口鼻も)
- 吸引器
- SpO₂・カプノメータ・心電図・血圧計
- 吸引カテーテル
- エアウェイ(経鼻・経口)
- 声門上器具
- 喉頭鏡
- スタイレット
- 気管チューブ
- 気管挿管に必要な物品(カフ用シリンジや潤滑剤など)
- 鎮静薬・鎮痛薬・拮抗薬
実際の対応
舌根沈下や呼吸抑制が起きた場合、まずはとにかく応援を呼ぶ!
【気道確保】
- 頭部後屈・顎先挙上
- 必要に応じてエアウェイを挿入
- 必要に応じて気管挿管
【換気のサポート】
- 用手換気
- 必要に応じて酸素投与
【拮抗薬の使用】
- ミダゾラム(ドルミカム®)使用時→フルマゼニル(アネキセート®など)
- フェンタニル使用時→ナロキソン



「医師の指示を待つ」だけじゃなくて、私たちが何をすべきか知っておくことも大事だよね。
こんな時はこう動く!
ってイメトレしておくだけで、現場で焦らず対応できるかも!
おわりに
私自身も、執刀医+外回りの2人だけで局所麻酔手術を担当したときは本当にドキドキしました。
患者さんを見ながら、モニター管理、VS記録と大忙し。
でも、そんな状況だからこそ、
「どうすれば患者さんに安心して動かずにいてもらえるか」
「過鎮静が起きたらどう対応するか」
を常に意識することが大切だと感じています。
今回ご紹介した現場の声は、多くの手術室看護師の皆さんから寄せられた貴重な体験談です。
施設によって方針や使用薬剤は異なりますが、どの現場でも患者さんの安全を第一に考え、日々工夫を重ねている姿が伝わってきます。
「医師の指示を待つ」だけでなく、私たち看護師が何をすべきか知っておくこと。
こんな時はこう動く、というイメージトレーニングをしておくだけで、現場で焦らず対応できるかもしれません。
手術室での経験を積み重ねながら、患者にとって最善のケアを提供していきましょう。
【参考文献】
- 日本麻酔科学会:安全な鎮静のためのプラクティカルガイド
- 武田純三 編著:手術室の薬剤114.メディカ出版,p78ー84,2025