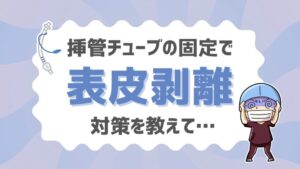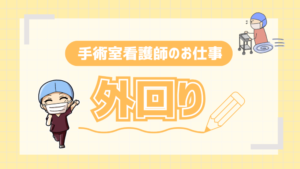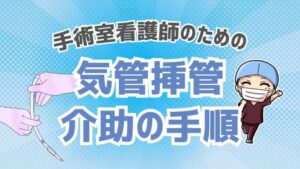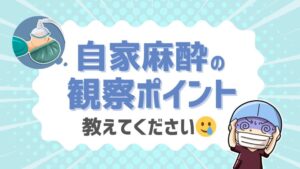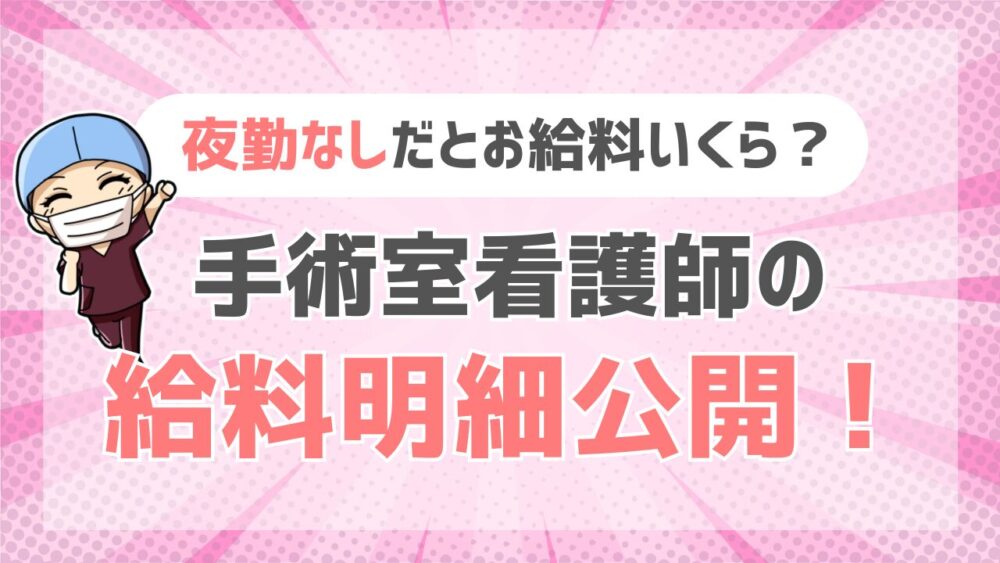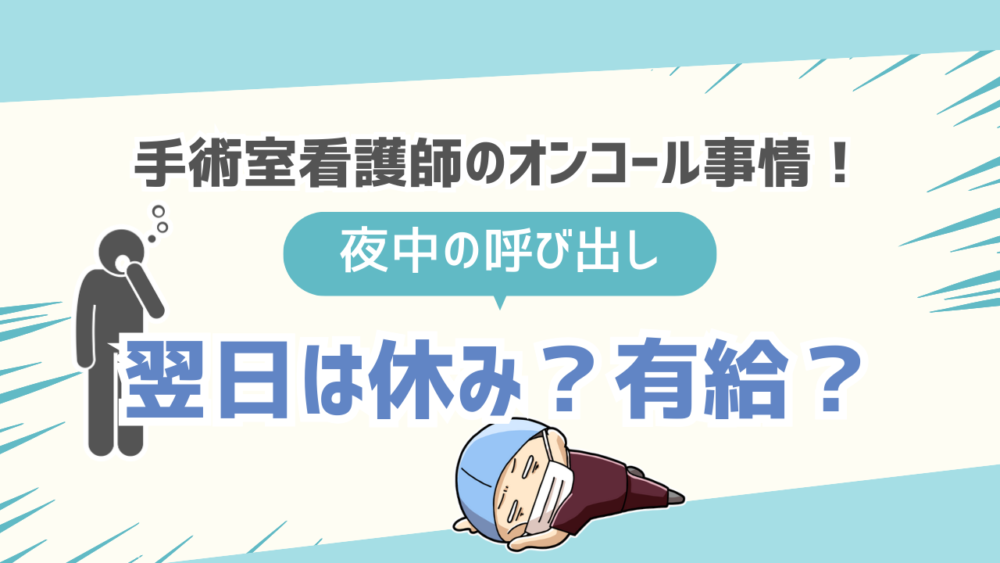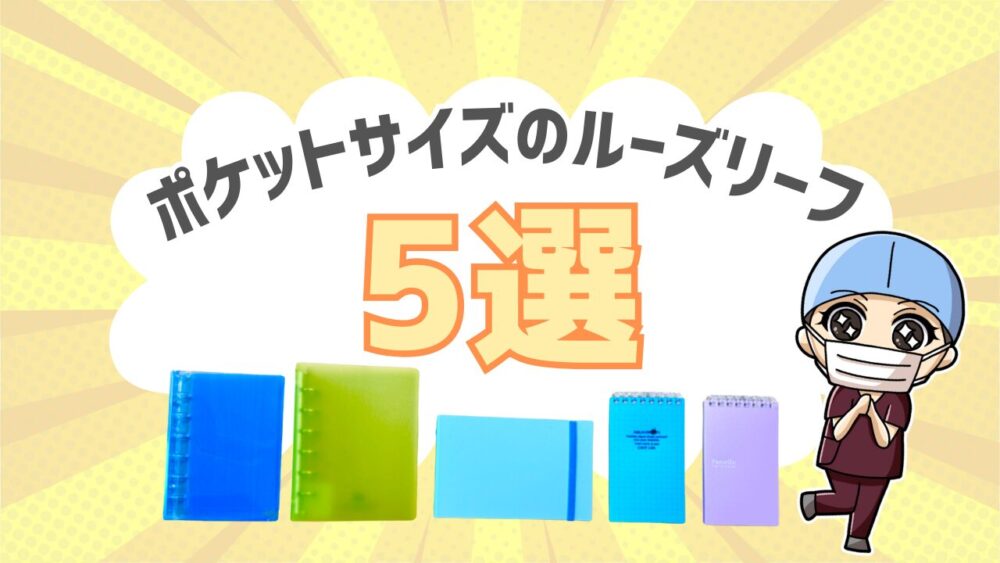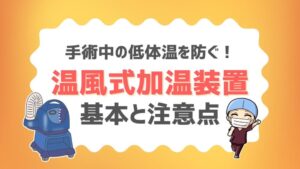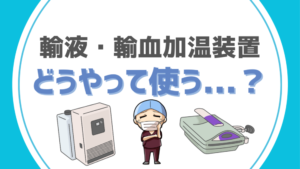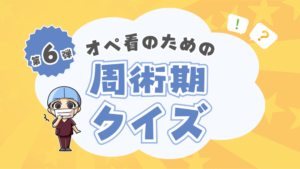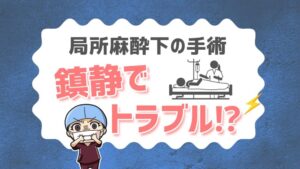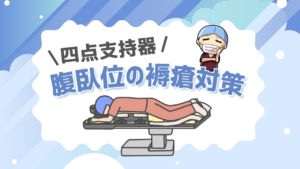手術前や手術後、「CVC入れるよ~!」と言われて、慌てて準備に走った経験はありませんか?
中心静脈カテーテル(CVC)の挿入は手術室でもよく行われる手技の一つですが、安全な施行のためには適切な準備と介助が欠かせません。
今回は、CVC挿入時の介助について、基本知識から実際の手順まで詳しく解説していきます。

自著
総合医学社「オペ看ノート」
メディカ出版「メディカLIBRARY」
エッセイ:オペナースしゅがーの脳腫瘍日記
クラシコ株式会社「NURSE LIFE MIX」
NLMメイトとして記事連載中
記事:オペ看ラボ
漫画:しゅがーは手術室にはいられない
\フォロワー5万人/
Instagramはこちら
中心静脈カテーテル(CVC)とは?

手術中は、状況に応じて複数の血管内留置カテーテルを入ることも珍しくありません。
麻酔薬や循環作動薬の投与、大量輸液や輸血、中心静脈圧のモニタリングなど、目的によって使い分けが必要になります。
だからこそ、それぞれのルートが「どこに入っていて、何のために使われているのか」をちゃんと理解しておくことが大切です。
中心静脈カテーテル(CVC)ってなに?
CVC(central venous catheter)は中心静脈カテーテルの略称で、静脈からカテーテルを挿入し、中心静脈から輸液や薬剤などを投与するラインのことです。

「CV入れるよ~!」とか略されることも多い。
- CVC:中心静脈カテーテル(central venous catheter)
- CV:中心静脈(central venous)



ちなみに、「中心静脈」とは上大静脈と下大静脈の総称💡
末梢静脈カテーテルと中心静脈カテーテルの特徴
主に輸液を投与するラインとして使用されるのが、「末梢静脈カテーテル」と「中心静脈カテーテル」の2つ。
末梢静脈カテーテルは看護師が確保でき、輸液や薬剤投与に使われますが、刺激の強い薬剤では血管外へ漏出すると皮膚障害を起こすことも。
一方、中心静脈カテーテルは、内頸静脈や鎖骨下静脈、大腿静脈などの太い静脈から挿入されます。
確実なルート確保ができ、安定して急速輸液や高カロリー輸液、薬剤投与ができる点が特徴。
中心静脈圧の測定も可能で、ICUや術後管理にも欠かせないラインです。
| 末梢静脈カテーテル | 中心静脈カテーテル |
|---|---|
| 末梢静脈路から、薬剤や輸液などを投与できる | 中心静脈から薬剤や輸液などを投与できる |
| ・看護師でも血管確保ができる ・薬剤が血管外へ漏出すると、皮膚障害を起こしやすい | ・医師が血管確保を行う ・中心静脈圧の測定ができる ・確実なルート確保ができる ・致死的な合併症が起こりうる ・血腫・気胸・感染・心膜を貫くことによる心タンポナーデなど |
主な挿入部位と特徴
中心静脈カテーテルの主な挿入部位には、内頸静脈、外頸静脈、鎖骨下静脈、大腿静脈などがあります。
内頸静脈は穿刺しやすく、気胸のリスクも比較的低め。
外頸静脈はランドマーク法やエコーガイドが不要な場合もありますが、挿入はやや難しい傾向があります。
鎖骨下静脈は術後管理がしやすい反面、気胸や血胸のリスクがあり注意が必要です。
大腿静脈は穿刺が容易で緊急時にも使われますが、大腿動脈の誤穿刺や静脈血栓症のリスクが高いため、状況に応じた選択が重要です。
| 内頸静脈 | 穿刺が行いやすい 気胸のリスクが低い |
|---|---|
| 外頸静脈 | 穿刺時に超音波によるガイドやランドマーク法が不要 カテーテル挿入が難しい |
| 鎖骨下静脈 | 術後管理が行いやすい 気胸、血胸のリスクが高い |
| 大腿静脈 | カテーテル挿入が容易 大腿動脈穿刺や静脈血栓症を併発するリスクが高い |
トリプルルーメンの構造と使い分け


手術室でよく使われるのが「トリプルルーメン」タイプ。(輸血を行う可能性があったり、麻酔用に使用されたりする)
名前の通り3つのルーメン(管腔)を持ち、それぞれの性質に応じて使い分けることができます。
| ルーメン | 特徴 | 使用用途 |
|---|---|---|
| 遠位 DISTAL | 内径が太く、高流量 | メインの輸液、急速輸血、中心静脈圧(CVP)測定など |
| 中間位 MEDIAL | 内径が細めで、安定した流速 | 低流量の配合変化が少ない薬剤の投与に適している |
| 近位 PROXIMAL | 内径が細め。カテーテル先端から最も遠いところから薬剤が流入する | カテコールアミン系など、フラッシュしてはいけない薬剤投与に適している |
中心静脈カテーテルの挿入・介助


カテーテル関連血流感染(CRBSI)
カテーテル関連血流感染:CRBSI(catheter related blood stream infection)
カテーテル関連血流感染は、中心静脈カテーテルを介して血流に細菌などが侵入することで感染症を引き起こす状態です。
発熱・悪寒・戦慄など、敗血症症状を引き起こすリスクがあり、場合によっては命に関わることも。
特に中心静脈カテーテルは太い静脈に直接アクセスしているため、一度感染が起こると全身への影響が大きくなります。
防ぐには、挿入時の無菌操作やマキシマルバリアプリコーションの徹底がとても大事です。
マキシマルバリアプリコーションの5つ
- キャップ
- マスク
- 滅菌ガウン
- 滅菌手袋
- 滅菌ドレープ
この5つをしっかり着用して、無菌操作で施行することが大事です。



だから、CV入れるよ~って言われたら、先生のガウンと手袋も準備するよ!
必要物品
- 中心静脈カテーテルセット
- 滅菌ドレープ(中心静脈カテーテルセットに入っていることもある)
- ガウン、清潔手袋
- 消毒薬(イソジンなど)
- 局所麻酔薬(キシロカインなど)
- 生理食塩水
- エコー本体と滅菌エコープローブカバー(超音波ガイド法の場合)
- シリンジと針
- ヘパリンロック
- 輸液セット(必要時)
穿刺法
| ランドマーク法 | 超音波ガイド法(エコーガイド法) |
|---|---|
| 解剖学的な目印をもとに挿入する方法 | エコーガイド下で挿入する方法 |
| 専用機器がなくても挿入できる 視覚的な確認ができないので、動脈穿刺や気胸などのリスクが高い | 超音波機器(エコー)の準備が必要 リアルタイムで静脈や針の位置を確認できるので、動脈穿刺や気胸などのリスクが低い |



超音波ガイド法の時はエコー本体と滅菌エコープローブカバーを準備!
中心静脈カテーテルの挿入時のプローブカバーの介助


※プローブカバーに滅菌ゼリーが入っているものもある。


不潔なのは袋の内側だけ!
外側は清潔!触っちゃダメ!
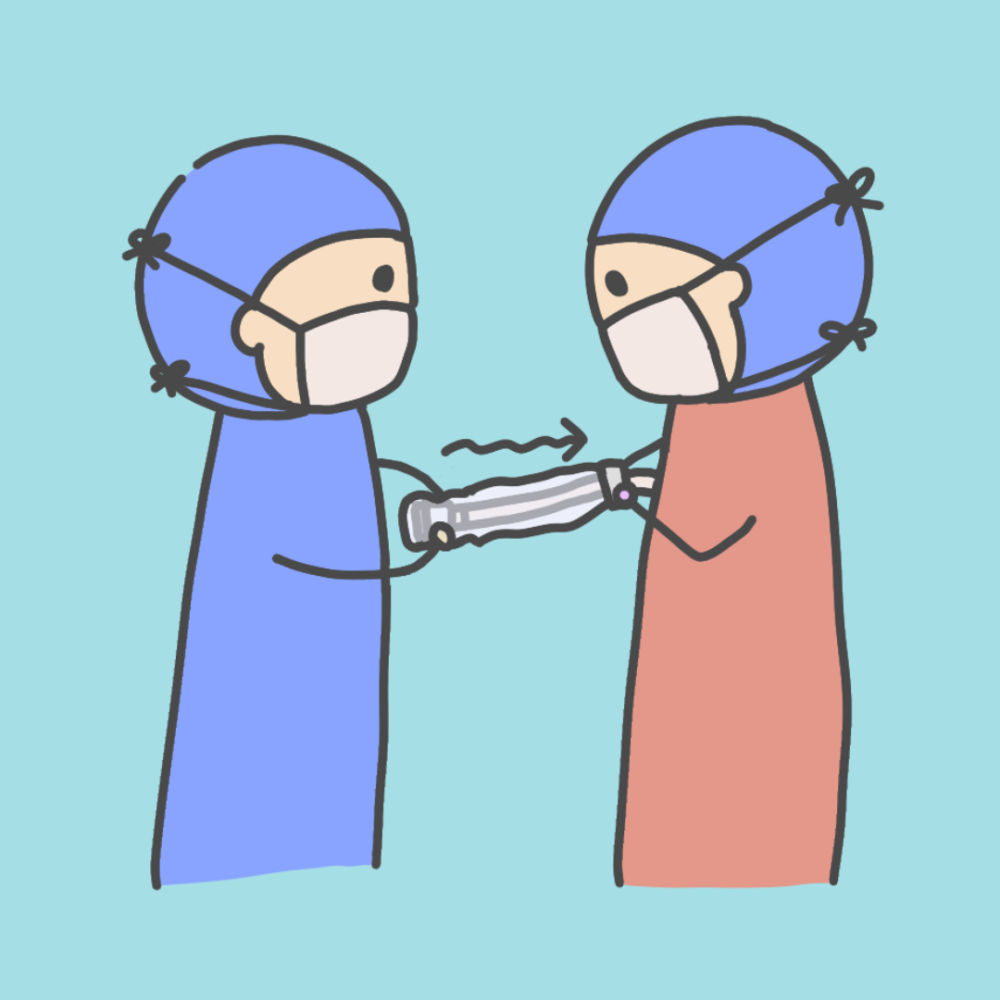
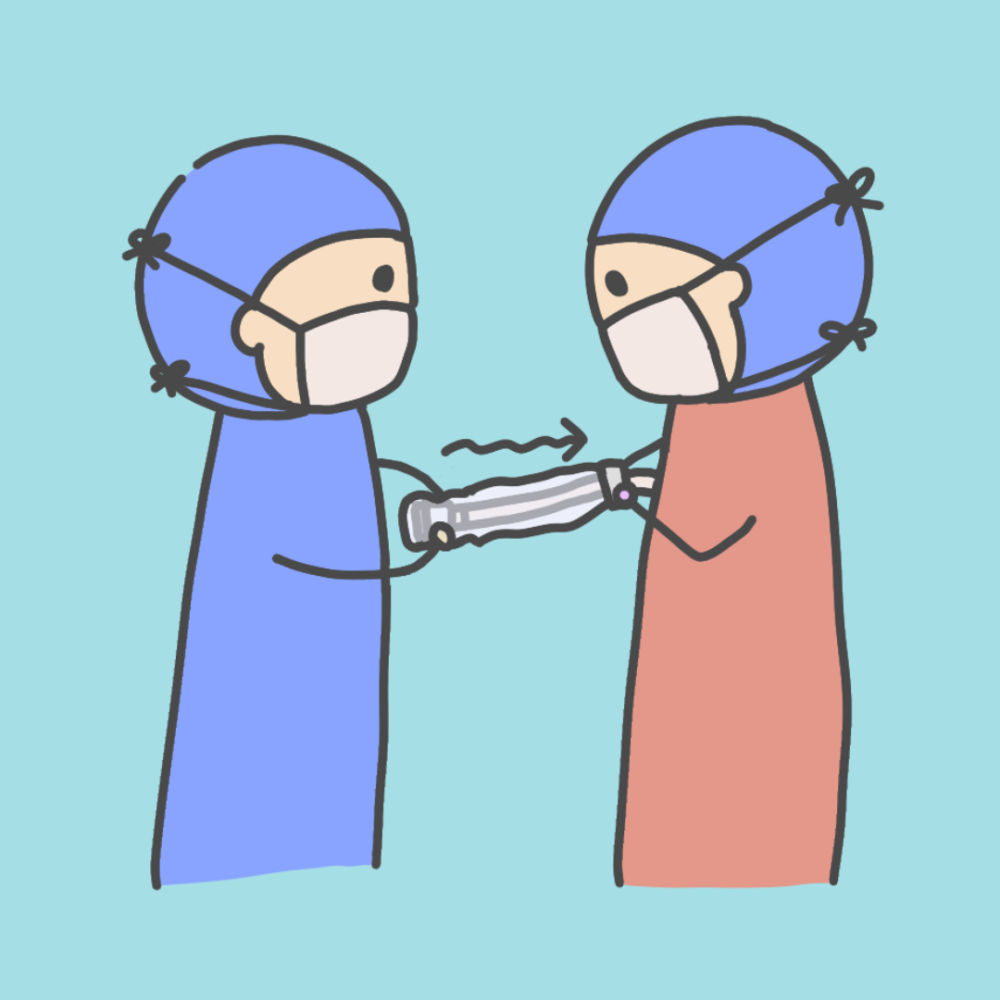
穿刺の手順
医師が行う
投与前に患者に声をかける。
看護師が行う(ことが多い)
病棟への申し送り
中心静脈カテーテル挿入後は、以下の内容を病棟に申し送りします。
- 何センチ固定なのか
- カテーテルの種類
(シングルなのか、トリプルなのかなど) - カテーテル挿入部位の皮膚の状態
- 合併症の有無(特に気胸)
- 医師の指示(あれば)
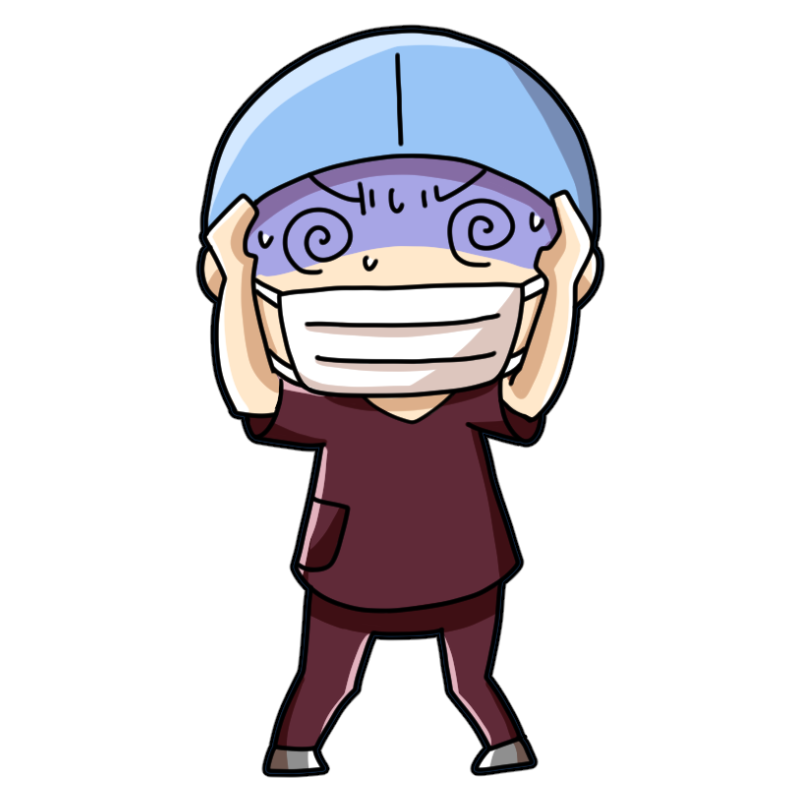
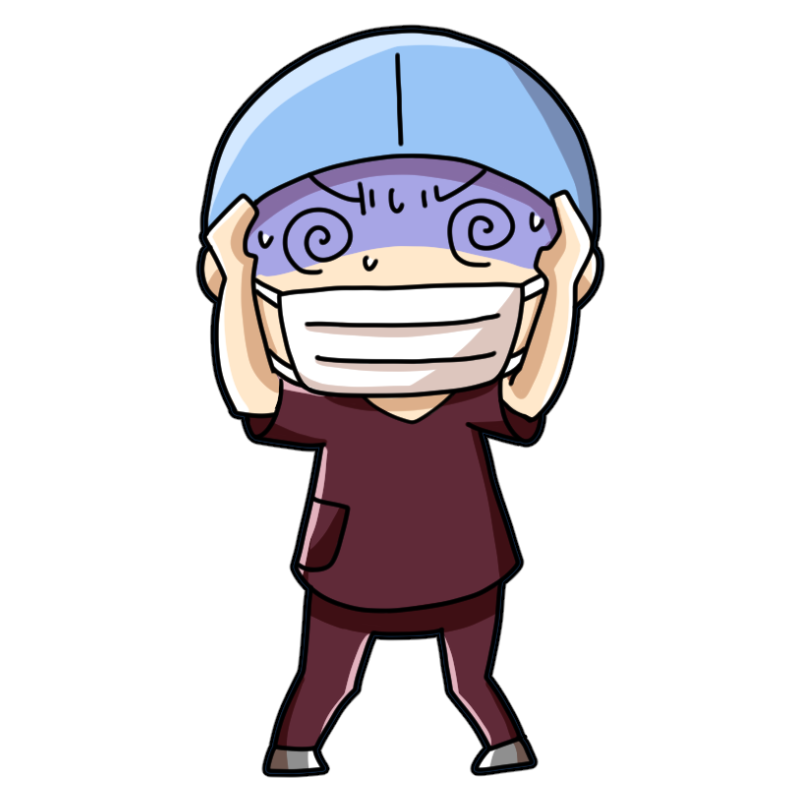
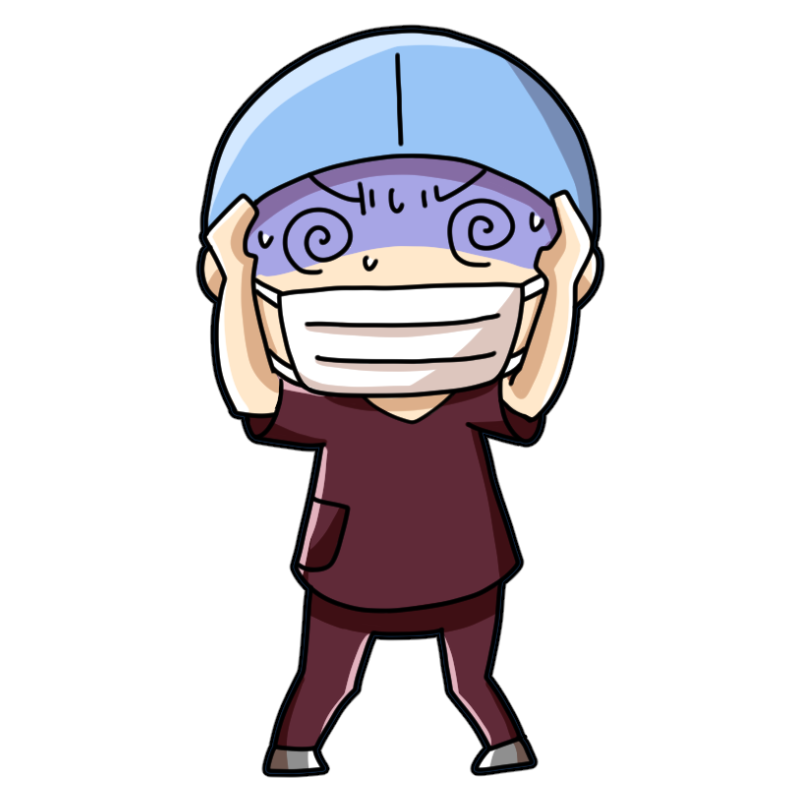
ちなみに、挿入直後に起きやすい合併症は気胸!
低酸素血症、心拍数の上昇、血圧低下など…
おわりに
中心静脈カテーテル挿入は、術中・術後管理に欠かせない大切な処置のひとつ。
ですが、感染や合併症などのリスクも伴うため、安全に行うためには適切な準備が必要です。
特に、マキシマルバリアプリコーションの徹底や、使用するルーメンの使い分け、穿刺部位ごとの特徴の理解など、手術室看護師として押さえておきたいポイントはたくさんあります。
いざ「CV入れるよ~!」と言われたときに焦らず動けるよう、日ごろから知識を整理しておけるといいですね。
【参考文献】
- はっしー・大田和季 著:輸液の違いがわかる! ナースのメモ帳.メディカ出版,p88ー93,2025
- 日本麻酔科学会・周術期管理チーム委員会 編著:周術期管理チームテキスト第4版,日本麻酔科学会,p243ー245,2021
- 浅井貴子:ルート&カテーテル類の管理 (作成、介助など).オペナーシング 36(9):22-26,2021
- 飯塚由記:vol.3【術中編】カテーテル管理の掟.オペナーシング 38(3):56-57,2023
- 外科医TEE! 編著 :外科研修おたすけBOOK.メジカルビュー社,p26-32,2025